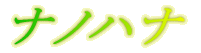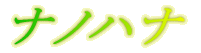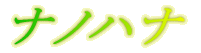♪ 灯かりを点けましょ、ボンボリに〜 お花をあげましょ、桃の花〜
3月3日が近づくと日本中で聴こえるイベントソングといえばコレだ。
所謂る女の子のお節句の日。
日本中がそのお節句のお祝いで一色に染まると言っても過言ではない。
人形屋やらお菓子屋やらをメインに最近では雑多な業種が手を変え品を変え、消費者意識を煽る謳い文句を並べ立て、
こぞって販売商戦を繰り広げる女の子の一大イベント。
とりわけ、女児を抱える家庭では切実に凄まじい世間への見栄と親馬鹿根性丸出しの日となるわけで。
3月といえば日本人なら誰でも思い浮かべるのが雛祭なわけだけど。
サンジは煙草を咥えたままの唇を微細に歪めて街を彩るディスプレイを見遣ると遠い昔に思いを馳せた。
「ねえ、私の家のお雛様見においでよ」
「あ、ずるい!私の家が先よ。ね、来てくれるよね?」
サラサラの金髪に青い瞳の外見をしたサンジは日本の女の子たちによくモテる。
子供心にもサンジの外見が童話の中の王子様を具現化しているように思うのだろう。
もちろん、その母親たちにも。
大好きな女の子たちに囲まれてサンジは内心では鼻の下を伸ばしきっていた。
愛くるしい天使の表情で頬を桜色に染めて上目遣いに「僕が遊びに行ってもいいの?」なんて、なんとも殊勝な言葉を
小さく伝えると目の前の女の子たちが大きく力強く頷くのが見えてサンジは花開くような笑みを零した。
「もちろんよ。絶対に来てね」
「うちもママがご馳走作ってくれるから!」
「私の家だってそうよ。だから、ね、サンジくん、来てちょうだいね」
そう言ってサンジの手をぎゅっと握ってくれるクラスメートの女の子たちにサンジも約束のために確りと頷いた。
「必ず行くからね。僕にもお雛様見せてね」
女の子同士の熾烈な戦いは幼稚園の年少さんどころか、公園デヴューのホンの小さな幼児の頃から既に始まっていた。
こと雛祭に関しては特に筆舌に尽くし難い白熱振りで男の子とその両親をも唖然とさせたものだった。
この時期、女の子たちの、人気のある男の子へのアプローチときたら、そりゃもう大人顔負けで。
常日頃、自分が好きだとか、かっこいいと意中に思っている男の子が自分の家の雛祭パーティーに来てくれるかどうかが
人生の一大事と言わんばかりに熱意をこめてお誘いをかけてくるのだから、これを熾烈と言わずして何と言う、という
感じなわけで。
とにかく、だ。
自分の雛人形の自慢から始まって母親の手料理やらホームパーティーの出来にまで親子揃って見栄を張るのだから
凄まじいなんてもんじゃあない。
それに引き換え、5月の端午の節句―男の子のお祭りだろうソレはなんとも長閑であっさりした感が拭えない。
いや、なまじ近代において「こどもの日」という名称を付けられた結果、こども全般に対する日となり、男の子の
お節句だけでは済まなくなったせいか。
サンジは幼稚園の年少さんの頃には既に女同士のバトルの真っ只中に放り込まれて揉みくちゃにされてきたので
小学校低学年の現在では女の子たちのあしらいも板についてしまった。
当時、クラスの女の子たちとその母親にとってはサンジのような外見の男の子を雛祭の日に自分の家のパーティーに
呼ぶのは一種のステータスらしかった。
親は見目麗しいものを自分の子供とその雛飾りと一緒に並べてみたいようだった。
女の子は女の子でサンジの金髪・碧眼の外見が王子様的憧れを満足されるらしく、ましてサンジは女の子には優しいから
雛祭は特に構ってほしがる傾向が顕著に出た。
他と明らかに毛色の違うサンジは彼らにとっては見せ物の1つ、余興の1つ、下手をすると雛祭のお飾りの1つにしか
過ぎないことを彼は幼いながらも既にイヤというほど思い知っていた。
お家に招かれて、まずさせられるのは雛人形の前でその家の女の子と、はたまたその家族と一緒に写真に納まることから
始まるのだから。
ひどい家になるとポーズまで指定されたりして流石のサンジも閉口したこともある。
―つまり「私には外人の友達がいたのよ」という将来の自慢話のタネ作りでしかない。
アルバムの中の自慢の1コマを作るための。
でも生来の女好きなサンジにとっては女の子たちと愉しい場を持てるというオイシくて嬉しいことには変わりがなくて。
どこのお家にお呼ばれしてもキチンと服装を整えて一丁前に小さなプレゼント―この場合、サンジが焼いたクッキー
だったりケーキだったりだけれど―を持参して女の子を喜ばせることには甲斐甲斐しくも余念がなかった。
だから。
その女の子のお祭りの前日が自分の誕生日だなんて話題は誰にも言ったことがなかった。
この時期、クラスの女の子たち皆の話題は雛祭に向かって突き進んでいて、誰の口からもサンジの誕生日の話が話題として
上ることがなかったから。
そんな中、自分で自分の誕生日の話を持ち出すほどサンジは厚かましくもずうずうしくもなかった。
だから。
サンジは幼稚園、小学校と日本の教育課程を進んできたけれど、これまで友だちに誕生日を祝ってもらったことがなかった。
まあ、男の子の大半がそういうイベントの類には頓着しないものだけれど。
それでも一抹の淋しさは付き纏っていた、世間が雛祭で賑わえば賑わうほど。
たった1日の違いを羨んだりした。
小学校での学校生活もあと僅かという6年生の3学期。
4月から通う中学校の制服やらその他の必要なもののオーダーも終わり、学校では、そろそろ卒業式の練習で授業が潰れる
ことも多くなってきた、そんな頃。
午前中だけの短縮授業で学校から帰宅して夕飯の支度に取りかかるまでにはまだ時間が少し早すぎてサンジは何をするでも
なく暇さにあかせてテレビをつけて観ていたら「ピンポ〜ン」と来客を告げる呼び鈴が短く鳴った。
「はーい」
まだ変声期を迎えていない澄んだ高めのボーイソプラノの声でサンジは玄関へ向かう。
「どちらさまですか?」
不用意にドアを開けてはいけないと同居の祖父に口煩く言われているから念のためにそう言ってみる。
と、ドアの向こう側から「・・・俺だ」というくぐもった声が聞こえた。
え、・・・?
明らかに子供の、同じ年頃の声だと判るのだけれど特定できなくて。
というより「あいつが訪ねてくるなんて有り得ない」と咄嗟にサンジは思った。
いや、あいつがサンジの家の住所を知っているかさえ怪しい。
慌てて玄関の鍵を開けてドアを開くと顔の真正面一杯に、玄関を塞ぐように大量の黄色と緑が出現してサンジは顔を仰け反らせた。
「なっ・・・」
「あ、悪りい」
言いながら一歩後ろに下がった相手を離れた距離の分だけで検分する。
少し照れたような顔をしているけれど見慣れた緑色の頭髪は間違いなくクラスメイトのゾロのものだった。
「なんだよ、いったい。てめえ、どうして・・・」
そもそも、どうしてゾロがサンジの家を訪ねてくるのかと疑問が浮かぶ。
サンジが怪訝そうに問うのに当のゾロは意に介した風もなく「これやる」と両手一杯に抱えていた菜の花をサンジの手に
押し付けてきた。
「え、えっ・・・?」
「お前、今日誕生日だろ。だから・・・」
両手に持ちきれないくらいの菜の花を半ば強制的に渡され、両手でずしりと重いそれを抱えてサンジは困惑した。
「心配すんな、ちゃんと虫は掃ってきたから」
なんで、どうしてそんなこと、こいつが知ってんだよ・・・
「どうして・・・?」
思わず口を突いて出ていた。
ゾロが正面で緑色の頭髪をガリガリと掻き、視線を逸らせてポツリと言った。
耳朶が赤い。
「てめえが去年、俺の誕生日にアレくれたじゃねえか」
そう言われて、「ああ」とそんなこともあったかとサンジはようやっと思い出す。
サンジとゾロは去年の4月に6年生に進級して初めて同じクラスになった同士だ。
何故かソリが合わなくて何をするにつけても喧嘩になり、クラスで1番のトラブルメーカーで、担任の教師泣かせな面倒を
起こす二人だった。
二人の間はずっとそんなだったのに。
卒業を間近に控えてその関係は尚、変わることはないように思えていたのに。
昨年の11月11日。
学校で、お休み時間中にクラスの女の子たちの他愛ないお喋りを聞いている時にサンジはその「1」が4つ並んだぞろ目の日が
ゾロの誕生日だと知った。
何を思ったのか―たぶん本人でさえ理由を覚えていないかもしれないが―、サンジは抹茶を混ぜ込んだパウンドケーキを焼いて
ゾロに渡したのだ。
抹茶を混ぜたのはゾロの頭髪を思い浮かべたせいもあるが決してイヤミではなかった。
「これやるよ」
学校の下駄箱で帰ろうとしているゾロを呼び止めて一言そう告げてサンジは持っていた包みを差し出した。
けれど普段は寄ると触ると喧嘩しかしていない相手に何か渡されても安易に受け取ることは普通考えつかないのが当然で。
茫然とするゾロの手に無理やり押し付けるように包みを渡してサンジは続けた。
「てめえ、今日誕生日なんだってな。1が4つも並ぶなんてすっげえな!」
そう言って屈託なく笑ったのだった。
それが、たぶんゾロに向けた最初の友好的な笑顔だったと思う。
サンジだって、もう1日違えば「3」が2つ並んだのにと、ちょっと悔しくて。
でも、だからこそ数字が並ぶという偶然を凄いことと純粋に思えたのだ。そんなふうだったと今にしてみれば自分の気持ちを
理解できるし納得がいくのだけれど。
あの時は、ずっと仲良くできなかったゾロにたったそれだけのことでパウンドケーキを手渡すことが無性に恥ずかしくて
押し付けるように手渡して言いたいことだけ言って、さっさと帰ってきてしまったからゾロがその後、そのケーキを
どうしたのかとかそんなことには気が回らなかったし、ゾロのほうに何か反応があればまた違っていたかもしれないけれど、
ケーキを受け取ったゾロからはその後、何も反応がなくてサンジもそのことをすっかり忘れていた。
翌日からまた喧嘩を繰り返していたし。
それが今頃になって。
「あん時くれたケーキ、お袋に大好評だった。俺のだって言ってんのにバクバク喰いやがって、もう少しで半分以上喰われちまう
トコだった」
って、ことは半分はゾロが食べたということだ。
「お前、あれ喰ったのか?」
訊かれてゾロは、しっかりと頷いた。
「美味かった」
言葉まで付いてきてサンジは目を見開いた。
「は・・・そうか」
サンジは肩の力が抜けるのを感じた。心なしか頬や耳がやたら熱い気がした。
「なあ、時間大丈夫か?ここで立ち話もナンだから良かったら上がれよ」
嬉しくて緩む頬をそのままにしてサンジはゾロを誘った。
そんなやわらかな顔つきにゾロが驚愕していたことなどサンジは知らない。
「俺以外、誰もいねえから遠慮しなくていいぜ」
「・・・・・おう」
僅かの沈黙の後、ゾロは返事をしてサンジに続いて玄関の中へと足を進めた。
とりあえず花瓶では間に合いそうにもない量なので水汲み用のバケツに水を張り、ゾロが持ってきてくれた菜の花の山をそのまま
挿しこんだ。
「紅茶でいいか?なあ、腹減ってねえ?」
言いながら水を入れたケトルをコンロにかける。
「ぁ・・・そういや、ちっと減ってっかな。爺ちゃんの畑から直行したから」
自分の腹を見下ろして押さえながら素直な返事が返る。
「桜餅あんだけど喰う?」
「おう、もらってもいいのか?」
「ああ。やれねえモンを勧めたりしねえよ。じゃあ緑茶のほうがいいな」
なんか学校ン時とは態度が全然違うのな、こいつ
食器棚のほうへ行き、手馴れた仕草で茶器やら小皿を出しているサンジを眺めて感じたことを脳内で言葉に変換していると
当人がいきなり振り返ってこちらを見るからゾロは内心で慌てた。
「突っ立ってないで適当にその辺に座ってろよ。あ、その前に手洗え」
言われてゾロは水道で手を洗い、テーブルの一角に居場所を見つけて椅子を引き出して座った。
程なくして湯の沸く音がして後、馴染んだ緑茶の香りがゾロの鼻腔を擽った。
「お待ちどうさま」
サンジが優雅な手つきでゾロの前に茶器と小皿に載せられた桜餅を置いた。
「美味そうだな」
「ああ、めちゃくちゃ美味えぞ」
サンジもゾロの正面に座ると自分の分のお茶をずずーっと啜った。
「いただきます」
両の手を合わせてきっちりと挨拶を口にしてから桜餅を摘み上げたゾロをサンジは驚いた顔で見つめた。
行儀いいじゃん・・・
てっきり、そのままガブリと喰らいつくのだろうと思っていたのに予想外に礼儀正しいゾロの仕草にサンジは嬉しさを感じた。
「美味えっ!」
一口頬張って感嘆の声を上げるゾロの顔は嬉しそうでサンジは満足そうに笑った。
「当たり前だって。そりゃあ俺の自信作だ」
「え、お前が作ったのか?こんなもんを作れるなんてお前、凄えな」
ゾロが素直に褒めるものだからサンジのほうが照れてしまった。
頬が赤くなるのが解かる。顔に血が上る。
「明日は雛祭だからな」
話題を逸らせたくてサンジは言葉を繋ぐ。
「女の子たちの家にお呼ばれしてっから手土産に持っていこうと思ってさ」
なるほどと納得したように頷く。
「けど、今日はお前の誕生日だろ。他人のことはいいから自分を祝えよ」
「え・・・」
「去年、自分の誕生日にお前にケーキもらって嬉しかった。俺、他人に誕生日を祝ってもらったのってあれが初めてだ。
嬉しくて、こりゃあ俺もお前の誕生日に何かしてやりてえって、ずっと思ってた」
ゾロが滔々と語るように喋るのでサンジは口を挟むことも忘れて聞き入っていた。
「何をやったらお前が喜ぶかって散々悩んだ。よく考えたら俺ら喧嘩ばっかりしてっしよ」
1度、ずずーっとお茶を啜って口を潤して続いて飛び出た言葉にサンジは目を丸くした。
「でも、俺は別にお前を嫌ってるわけじゃねえ」
「えっ!」
ゾロが。喧嘩ばかりしているゾロがサンジを嫌いじゃないと言い切ったのだから驚くなというほうが無理だ。
「・・・・・俺だってそうだ」
どきどきと煩く鳴り響く胸の鼓動が信じられないくらい大きく耳に届いて、もしかしたら口から心臓が飛び出てくるんじゃないかと
サンジは思って、そーっと胸に手をやった。
「うん、解かってる。でも、そんなだからお前の好みそうなモンとかが判らなくてな」
ゾロが遠くを見る目をした。
ゴクリと喉が鳴ってサンジはコホンと誤魔化すように咳払いをした。
その先を聞きたいような聞きたくないような焦れた感覚に身悶えしそうだった。
「ここんトコロずっと考えて考えまくってて、それでも思いつかなくて。とうとう今日が来ちまって、学校からの帰りに爺ちゃんに
相談しようと思って畑に行ったらアレが咲いてて」
そこまで言ってゾロは照れたように視線をバケツに流してポリポリと頭を掻いた。
「畑の中で威風堂々と風に揺れてる丸くて黄色いのを見たらお前の頭みてえって思ってよ」
その先は言い辛そうに
「両手じゃ持ちきれねえくらいたくさんの菜の花をお前に持たせてみてえなって思った。その菜の花の束の中でお前が笑う顔が
見てえなって・・・」
それはきっと間違いなく綺麗だろうなとゾロは思ったのだ。
想像したら、どうしても見たくなった。見たくて堪らなくなって祖父に畑に咲き乱れている菜の花をくれるように頼んでいた。
爺ちゃんは何を勘違いしたのか「ほお、好きな子でも出来たか?」とか「ゾロ坊もお年頃じゃのう」とか言って笑っていたの
だけれど、それは言わないでおく。
「お前、理科の屋外学習中か何かの時に虫が嫌いとか言って騒いでたろ。だから、ちゃんと落としてよ・・・」
なんだかジーンときてしまった。
ゾロの、普段は口数の決して多くないゾロの一言、一言が胸に沁みてきてサンジはヤバいと思った。
サンジが虫嫌いと知って、あれだけたくさんの菜の花全てから虫を取り払ってくれたのだと言う。
俺、泣きそう・・・かも
俯いて垂れた前髪で顔を隠す。
「だから結局お前の好みとかじゃなくなっちまったんだけどな。ん、どうした?」
俯いたままのサンジが、常の彼らしくなくてゾロは首を傾げる。
僅かに下がった視線の先で、ずずずーっと鼻を啜る音がしてゾロはギョッとした。
「な、なんで泣くんだよ」
俺がイジメてるみたいじゃねえか・・・
普段は好戦的とも思えるサンジの態度にすっかり狼狽えてしまった。
「泣いてねっ」
啜り上げたせいか、ガキくさい言いようになった。情けない半泣き声で反論を口にしても、その声は微かに震えていて。
「こんなモンをもらうのはイヤだったか?」
サンジが外見に似合わず、女の子扱いをされるのを嫌うことを思い出してゾロは血の気が失せる気がした。
花なんて、まんま女扱いじゃねえか・・・
ヤバいと思ってこめかみと口元が引き攣った。
「ち、違えよっ!」
ゾロが困惑に柳眉な眉を寄せたのに気づいたサンジは勘違いに慌てて声を荒げた。
反射的に顔を上げてしまってサンジは涙の溜まった目をゾロに見られてしまった。
「!!!」
初めて見るサンジの涙の載った目許は青い色を更に綺麗に強調してみせた。
まるで青い海に立つ波のようだと思った。
もっと見ていたいと思ったのにサンジは、ささっと視線をテーブルの上へ落としてしまった。
しばらく二人の間に沈黙が落ちた。
ゾロが何も言わないからサンジは居心地悪げに身を捩ると観念して口を開いた。
「・・・すっげえ嬉しいよ」
自分と違って、ほっそりとした白いサンジの指がテーブルの上をモジモジと動くのへ目が吸い寄せられる。
「俺も・・・他人に誕生日を祝ってもらったことなかったから。だから・・・」
言い淀んでいたかと思った次の瞬間にガバリッと伏せていた顔を上げ、ゾロのほうを見たサンジは花が咲き綻ぶようにふわりと
笑った。その拍子に目の縁に盛っていた透明な滴がひとすじ、つーっと薄い桜色に色付いた頬を伝って落ちていくのをゾロは
惚けたように見つめるしかできなかった。
「ありがとうな!」
満面の笑みを浮かべたサンジは、いつぞやにクラスの誰かが持ってきたポストカードに載っていた「天使」の絵そのものに見えた。
あの時は「そっくりだ!」とキャーキャー騒ぎ立てるクラスメートたちに呆れるばかりだったけれど今、ゾロはあのポストカードを
見つけた奴を素直に凄いと認められた。
あの天使は泣いてなどいなかったけれど。
こんな顔をされたら信心深い者ならば思わず膝を折り、拝んでしまうかもしれないとさえ思えるのだから不思議だ。
毎日のように喧嘩を繰り返した相手を見て、よもやそんなことを思う日がくるなんてゾロは想像もしなかった。
「・・・おい?」
ぼーっと自分を見つめるゾロにサンジのほうが痺れを切らして問う。
「あ、・・・ああ。俺のほうこそ遅れたけど・・・あン時はありがとな」
我に返って、サンジに礼を言われたことに思い至るとゾロは自分がサンジに礼の言葉を伝えていないことに気が付いた。
照れくさかったけれど素直に言葉を声に載せて伝えるとサンジが微笑みを深くして頷いたのが見えて一層強く「嬉しい」と
甘く感じた。
互いに見合って、どちらからともなく「へへへへ」と照れたように笑いあう。
一人同士の心が温かくなっていく。
「あとで、あの菜の花でお浸し作ってやるよ」
バケツに挿されたままの菜の花を指さす。
「え、お前、そんなモンも作れんのか?」
「おうっ。美味えの作ってやるからな」
他愛もない内容ながら会話が続く。
今までずっと喧嘩しかしてこなかった二人にとっては、やっと友だちとしての最初の一歩を踏み出したばかりで、どちらもまだ
硬さが抜けず、ぎこちないことこの上ないのだけれど。互いを見遣って時折、照れたように笑いあう姿が子供らしくて微笑ましい。
玄関でガチャガチャと鍵が開く音がしてサンジが「え?」と意識をそちらへ向けた。
「家族の人が帰ってきたのか?」
サンジの家の都合など知らないからゾロは考えもなく、そう訊いた。
「・・・まだ帰ってくる時間じゃねえ、んだけど・・・」
言いながら席を立つと玄関へ続くドアに向かった。
こんなことは初めてで、何かあったんだろうかとサンジは内心で不安を感じていた。
途端、そのドアが開き、サンジはビクリと躯を強張らせて後退さった。
そこへ変わった髭を生やした大きな人物が姿を現わしてゾロは目を大きく見開いた。
髭にも驚いたけれど、その威厳のある存在感にもその人物が只者ではないと感じ取っていた。
右足は義足らしく、杖のようなものを補助的に使って独特の歩き方をしていたがヨタつくような感じは全くない。
「なんでこんな時間にジジイが帰ってくんだよっ!」
先ほどの驚きぶりとは多少異なる顔つきでサンジが、その男を「ジジイ」と呼んだことでゾロは二人の関係を瞬時に理解した。
こいつの爺ちゃんか
「なんだよ、どうしたんだよ、店でなんかあったのかよ?」
ゾロからは見えなかったけれどサンジの形相には必死さが滲んでいた。
「うるせえぞ、チビナス」
「チビナスって言うな!」
二人のやりとりを聞きながらゾロは、ずずずーっと温くなってきたお茶をのんびりと飲んだ。― 度胸だけは一人前なゾロだった。
「ん、?てめえはコレのクラスメートか」
悠然とした態度のゾロに対して相手は問いのような、確認のような言い方をした。
「俺のクラスメートだよ!ゾロ、こっちは俺のジジイだ」
ついでのような言葉遣いで手短かすぎる紹介の仕方をするサンジに、ゾロもゼフも苦笑するしかなかった。
「お邪魔してます。ロロノア・ゾロです」
言ってぺこりと頭を下げたゾロの礼儀正しい、綺麗な動作にサンジは目を奪われた。
や、なんか、やっぱり行儀いいよ、こいつ・・・
椅子から立ち上がり、一礼をするゾロに対して、「ふむ」とゼフが頷く気配がした。
「チビナスの友だちにしちゃあ行儀がいいじゃねえか」
「なに気に失礼なこと言ってんじゃねえよっクソジジイ!」
ゼフの挑発を含んだ言葉にハッと我に返って、黄色い頭から湯気が立ち上るんじゃないかと思うほどサンジは真っ赤になって
怒鳴っている。
変わった髭の持ち主はサンジを見ないまま、ゾロに視線を向けて一瞬、その目を見据えると目尻を弛緩させた。
髭を蓄えた下に見え隠れする口元が笑いを形作っているような気がした。
「坊主、今日はこの後、ナンか用事あるか?」
「何もねえ」
言葉遣いはイマイチなっちゃいねえなぁ
ゾロの返事に小さく苦笑いを浮かべた。
「おう、じゃあ坊主。家に夕飯は友だちの家でお呼ばれするからって連絡入れろ」
「「え」」
ゾロとサンジ、両方の口から同じ言葉が飛び出て結果、見事にハモッた。
サンジとて意味が解からなくて慌ててゼフを見遣った。
「どういうことだよ?急に早く帰ってきたり・・・俺、意味が解からねえよ」
大切な仕事の最中じゃなかったのかよと言いながらサンジの視線が上下左右に弱く揺れ始めて、ゼフは「やれやれ」と息を吐いた。
このガキは皆まで言わなきゃ解かんねえのか・・・いや、そうだろうな
馬鹿な子ほど可愛いというのは本当だろうかと多少情けない思いを、知らず零す溜め息に込めた。
「うちは、これからコレの誕生祝いをやる。坊主は参加できるか?」
サンジ本人へではなく、曲折してゾロへと問うゼフも臍曲がり度はサンジと張るのかもしれない。
ゼフに訊かれ、ゾロは言われた言葉の意味を正確に理解し、大きく強く頷いた。
「俺もこいつの誕生日を祝いたい」と素直に告げるとゼフの双眸が驚愕に見開いた後、目尻に皺を刻んで微笑みの形に変わった。
「おらチビナス、ぼーっとしてねえで坊主に電話の場所を教えてやらねえか」
ゼフとゾロの会話を聞いていたサンジは未だ思考回路が上手く作動せずに苦慮していたのに、そこへゼフの言葉が落ちてきて
反射的に返事が飛び出た。
「チビナス言うなってば!」
「うるせえっ、とっととやれ」
言いながらもゼフはキッチンへと移動を始めていた。見ると手には大きな紙袋が下げられていて中から食品の詰まった容器が
幾つも覗いていた。
「み、店はどうすんだよ!これから夜のかき入れ時だろうが!!」
ゼフはオドオドと戸惑いを露わにし始めたサンジをジロリと横目で睨みつけると
「てめえは何もかも言わなくちゃ解からねえボンクラか!」
一喝されてサンジはピタリと固まった。
「安心しろ。今年の3月2日は臨時休業だと何ヶ月も前から顧客どもには伝えてある」
客も従業員も皆、とっくに了承してんだ。馬鹿ナスめが。
そして休業を決めたのは1年以上前だ。
「え・・・」
「馬鹿が。今日は、てめえが12歳を迎える大切な節目の日だ。それを俺が祝ってやんなくて誰が祝うってんだ?」
ゼフの言葉を聞くサンジの目がどんどん大きく見開かれて。
そこに透明な膜が張ってきて潤み始め、まなこの堤防が決壊し、ぼたぼたと溢れて流れ落ち、白い陶磁のような頬を伝い。
顎の先からぼたぼたぼたっと床にまで滴って。
けれどサンジは微動だにもできずに立ち尽くしたままで目にゼフを一杯に映して見つめていた。
喰いしばらないと口から嗚咽が漏れそうでサンジは必死で歯を喰いしばっていた。
「今年、小学校を卒業すんだろが。そんなアホでどうする」
ゼフの目元がやわらかく笑うのを見たら我慢の限界がきてサンジは「ひうっ、くふうっ、えっぐぅ・・・」と盛大に嗚咽を
漏らして滝のように涙を溢れさせた。
鼻水とヨダレのオプション付きでエグエグと泣くサンジに、持っていた紙袋をキッチンのカウンターへ置いたゼフは義足とは
思えない素早さでサンジの前に立ち戻り、彼の金色の頭に手を置いてぐしゃぐしゃと撫で回した。
「馬鹿が・・・顔を洗ってこい」
言葉は悪いけれど、決して本意ではないことが解かるから。
小さく頷くサンジの頬に滑らせた大きな手で涙を拭ってやる仕草は愛情にまみれていた。
ばたばたと走り去るサンジを眺めてゾロは、さて、どうしたものかと思う。
家に電話をかけようにも電話機の場所が判らない。
「坊主」
呼ばれて視線を向けるとゼフが静かな表情でこちらを見ていた。
「好き嫌いはねえな?」
「ああ、問題ねえ」
口元が笑いに歪んでいるからゾロもニヤリと笑って返した。
そんなゾロの態度をガキのくせに豪胆じゃねえかと頼もしく感じて目尻の皺を深くした。
チビナス相手なら、こんくれえ度胸が据わってなけりゃあ付き合いきれねえか
くつくつと笑うゼフは、いかにも愉しそうで。
変なじーさん
ゾロがそんなふうに思って見ていたなんてことには気づきもしなかった。
サンジが洗面所から戻ってから電話の場所を教えてもらい、ゾロは自宅に電話を入れた。
母親が「はい、ロロノアでございます」と普段からは想像もつかない取り澄ました声で出たものだからゾロは最初ギョッとした。
そういえば自分の家に電話するのって初めてだと思う。
「あ、俺だけど」
気後れすることなく短く言うと受話器の向こうで『は?え、ゾロなの?』と僅かに驚いたような応答があった。
そりゃそうだ。急用でもできない限り小学生が自宅に電話をかけることなど滅多にない。
「今、クラスメートの家だ。俺その家で夕飯をご馳走になることになったから」
『えっ?!誰ちゃんのお家で?あんた、今のクラスにそんなお付き合いのお友だちなんていたっけ?ねえゾロ、あんた、そのお宅で
迷惑かけてやしないでしょうね?』
矢継ぎ早に疑問を投げつけられてゾロは閉口した。
めんどくせぇ・・・
ゾロが受話器を握りしめたまま、どうしたものかと躊躇していると後ろから手が伸びてきて咄嗟に振り向いていた。
「わしが代わろう」
ゼフが言ってゾロの手から受話器を受け取った。
「もしもし」
ゾロは大人のことは大人に任せようと、さっさと踵を返して先ほどのリビングへと戻った。
ドアを開けると先ほど座っていたテーブルにサンジの丸い金髪頭の後頭部が見えた。
「ぁ・・・」
ゾロに気づいて小さな声を発したサンジの顔が、さっと色付く。
「・・・さっきは取り乱して悪かったな」
言葉こそ大人びているけれど、かっこ悪いところを見られて恥ずかしいんだと理解してゾロはそれには突っ込まずに頷くだけに
とどめた。
あんだけ大泣きして見せたのだから照れがあっても不思議ではない。
ただ。
ゾロには、あの時、何故サンジがあんなに大泣きしてしまったのか、その理由は解からなかったから。
人ン家の事情は様々だしよ
喧嘩相手のゾロに見られてバツが悪いだろうにサンジはキチンとゾロに謝ってきたのだからサンジの名誉のためにもこの話題には
今後もふれないでおいてやろうと思った。
しかし。
「・・・あのよ」
サンジのほうから声がかかった。
「なんだ?」
「さっき無様なトコロを見せちまったけどよ」
サンジのほうが話を蒸し返してきてゾロは呆然とした。
こいつ馬鹿だ・・・人がせっかく黙っててやってんのに
「イイ歳してって思っただろ?でもな、違うんだ、ソレ・・・」
「あ?」
サンジの言っていることが解からなくて首を捻る。
「さっき俺、他人に誕生日を祝ってもらったことねえって言ったろ。実はさ、家族にも祝われた記憶がねえの」
にかり と笑う顔は少し痛々しい感じがしてゾロは自分の胸までがチクリと痛む気がした。
こんな平和な日本の中で、そんなことがあるんだろうかとゾロは思った。
サンジはいつだって明るくて賑やかで曇りなんて感じさせない明るい性格の奴だったから尚一層、たった今聞いた言葉が
信じられなかった。
「俺んちさ、さっきのジジイと二人っきりなんだ」
父ちゃんと母ちゃんはどうしたんだ?とは普段は気を遣わない系のゾロとしても言い出せなかった。
「ジジイはレストランを営ってんだけど。そこが結構、流行っててよ。年中忙しいんだ」
サンジからそこまで聞いて、だから今まで誕生日に構ってもらえることはなかったのだと理解し、納得した。
「レストランなんて客が来なきゃ保たねえだろ。だから忙しいのは良いことなんだ」
サンジは尚も喋ろうとする。けれど、先ほどからずっとテーブルの上の大布巾でテーブルの上を何度も、何度も拭いてばかり
いるし、その視線はどんどん下降している。
「もう何も喋んな。俺はお前の誕生日を祝えれば嬉しいし、どうやら美味いものを喰わせてもらえるらしいし」
何も文句はねえぞ、とサンジの金色の頭に手を置いて、さっきゼフがやったのと同じようにワシャワシャとかき回した。
この黄色いアヒルは、ずっと淋しさをこうやって我慢してきたに違いない
ゾロは「こんなエラい奴は大切にしてやんなきゃいけない」と思った。
本来なら、まだまだ親に甘えていたい年頃だ。それをサンジは、ずっと我慢していたのだ。
肉親に気を遣い、クラスの女どもに気を遣って、ほんと馬鹿なやつだなぁとサンジの懐の深さを推し測って、その健気さが胸を打った。
ゾロは決めた。
来年も、再来年も俺はこいつの誕生日を祝ってやる!ずっと祝ってやる!
目の前にあったサンジの大布巾を持つ白い手を上から掴んで、ぎゅっと握る。
掴んだ手から、サンジの躯がビクリと竦んだように感じられたが構わずに続ける。
「良かったじゃねえか」
言いながらゾロの顔が不敵に笑む。
サンジの垂れ目がちな青い目が大きく見開いて、その中にゾロを大きく映す。
「そのお陰で俺がお前の1番になれたんだから」
「なっ!!!!!」
瞬間湯沸かし器のようにサンジの顔が真っ赤に染まってゾロに掴まれた手を引っ込めようとするから。
「なにすっ・・・」
ゾロは手を強く掴み直してサンジの耳元に唇を寄せて言った。
「俺たち、これからは喧嘩だけじゃなくやっていこうぜ」
その瞬間のサンジの呆けた顔がマヌケすぎて堪らなく可愛かったことをゾロは一生忘れないと思った。
まだ赤くなれるんだと感心するゾロに手を握られたままでサンジは一瞬、呆けて。
ゾロに顔を覗きこまれて慌てて俯いて表情を隠したものの、でもしっかりと「うん」と頷いたのだった。
「あん時きゃあ俺様も可愛かったもんだよなぁ・・・」
煙草を咥えたまま、遠い目をして昔を懐かしむ自分を「俺は年寄りか!」と軽く叱責する。
何年経っても、この時期は街中のいたるところで雛祭ソングが流れているのが変わらない。
サンジとゾロの関係は中学に上がる頃には悪友と呼べるほどに一足飛びに変化し、周囲を驚かせた。
肩を並べて良いことも悪いことも一通りやってきた。
あの年以降、サンジの誕生日には決まってゾロが菜の花を持って家にやって来てサンジが作るご馳走を一緒に食べて、ささやかな
祝いをしてきた。
高校に上がる頃には、それに数人のメンバーが増えて賑やかになり。
あの日を境にサンジは誕生日を独りっきりで迎えることがなくなった。
高校を卒業して、それぞれ進路が変わっても仲間たちとは変わらずに親交を暖めあっている。若いうちに一生涯の宝だと思える
仲間たちと出会えたことは幸福なことだ。
そして、ゾロとサンジは今でも一緒だった。
友だちからコイビトへと互いの存在意義や立場は変わったけれど。
それでも変わらないのは互いを思いやれる気持ちと一緒に育んだ思い出の数々―――
ゾロがサンジにくれたもの
サンジがゾロにあげたもの
全部が愛しいものだから。
幸せだと素直に思えるくらい豊かに育つことが出来た自分の成長を褒めてやりたいと思った。
見慣れた街並みの向こうから更に見慣れた緑色の頭が見えてきた。
両手にいっぱいの菜の花を今年も抱えている姿にサンジが自然、笑む。
「ほんと、あいつのアレも馬鹿の一つ覚えだよな」
そう悪態を吐きつつも嬉しさは隠し切れない。
これで二人のあいだは始まったのだから。
サンジにとって大事な大事な思い出だった。
ゾロがサンジに気づき、手を上げようとして抱えた大量の菜の花と悪戦苦闘している姿に、ぷっと吹き出した。
馬鹿だねえ・・・どう考えたって無理だろ
仕方なくサンジのほうが合図に手を上げてやった。
今年もゾロが持って帰ってきたアレでお浸しを作ってやろうとサンジは思う。
ゾロが大股で、凄いスピードで近づいてくる。
「よお」
サンジに並び立つと、少し息を乱したゾロが挨拶をよこす。
「今年も大漁だなぁ」
「ああ。爺さんも、そのうち畑が菜の花で埋まるって言ってた」
ゾロのお爺さんはそう言いながらも愉しそうに笑っていたに違いない。
孫のゾロが菜の花をほしがる理由を彼も知っているのだ。
そして恒例行事になった菜の花をほしがる孫のために毎年お爺さんは自分の畑で菜の花を大切に育てている。
実際、ゾロが成長した分ずつ菜の花の量が毎年増え続けていることをサンジも解かっているのだ。
どんどん増える菜の花の量をサンジは嬉しいと思ってしまうのだから、もう打つ手もない。
普段、寡黙なゾロが、到底自分では花など買いそうもない硬派なゾロがサンジのためだけに1年に1回、こうして菜の花を
抱えている姿を見るのは至福としか言いようがないではないか。
その菜の花は虫嫌いなサンジのためにもうひと手間がかかっている。
畑で摘まれた後、ゾロの手によって1本ずつ丹念に駆虫されてから運んでこられてサンジの手へ渡されるのだ。そんなことも
最初から変わらない。
こんな愛情がいっぱい篭もった贈り物なんて世の中のどこにもない。
だからサンジは幸せを噛みしめて静かに、優しく笑う。
「じゃあ夕飯は今年も菜の花づくしだな」
「おう。またレパートリー増えたんだろ?」
「当然だろっ!」
ガッツポーズをとるサンジにゾロが目を細めて笑む。
「愉しみにしてる」
言いながら二人して肩を揃えて家路を目指す。
さあ、帰ろう
俺たちの家に
――― 今年からゾロとサンジは同じ家で一緒に暮らし始めた。
END
幸せな幸せなサン誕話を、いただいてしまいましたーっ(>▽<)/
うわーん、めぐみさんありがとうございます!
エロないけど(笑)エロないけど!幸せーーーっ!!
両手一杯菜の花抱えてやってくるゾロが素敵〜〜っv
視覚的にも春満載ですよね♪
飾るだけでなくてちゃんと食べる辺りがこの二人らしくて。
せっせと菜の花作りに勤しむ爺ちゃんは、孫の恋路を理解しているのかしら(心配)
ほんとにほんとに、素敵なみう誕ありがとうございました!