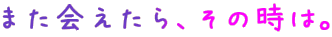
緑生い茂る森の中をさ迷い続け、何時間過ぎたことか。
おかしい。
わりと低い木に鳥が止まっていたところを右に曲がったはずなのに、 いくら探してもその木が見当たらない。
おかしい。
あの木、どこに行っちまったんだ。切られちまったのだろうか。
鳥がいつまでも同じ場所にいるはずもなく、そんな目印を頼りにしてしまったゾロは、そんなことには気付きもしない。
「なんだよ、もぅ!家はどっちだよ!?」
幼い体に胴着を着て、左手には木刀が1本握られている。
ロロノア・ゾロ、8歳。
この森を抜けたところにある、シモツキ村で暮らしている少年である。
緑色の髪に金色の瞳。固く閉じられた口はまっすぐに引き伸ばされ、意志の強さを窺わせる。一見すると賢そうな子供であるが、じつはそうでもない。重度の方向音痴。しかも無自覚。質が悪い。
世界最強の剣士になるため日夜修行に明け暮れているわけだが、今日は何を思ったか森の中で修行をしようと考えたのが運のつき。見事なまでに迷子中である。
ぐぅぅぅぅ。
「ハラへったなぁ・・・」
朝メシを食べた後に出てきてから何も食べていない。
大きな音を出すオナカをさする。さすったところで腹は膨れない。気休めにもなりやしない。
「どんぐり・・・食えないかな」
木に凭れかかり座る。地面にはたくさんのどんぐりがそこかしこに落ちている。が、食べられない。
はぁ〜、と大きくため息をついた。とたん更に空腹が襲ってくる。
「・・・父ちゃん・・・母ちゃ〜ん!」
叫んでみても、返ってくるのは己の木霊のみ。
「・・・父ちゃん・・・母ちゃん・・・ぅぅ・・・」
普段は勝ち気に振る舞ってはいるが、やはりどんなに大人ぶっても8歳は子供だ。
木しか目に入らない所では、一気に弱気になってしまう。
寂しくて怖くて、涙が滲む。
「ぅぅ〜・・・っく・・・」
膝を抱え頭を乗せる。
誰もいない空間にひとりぼっちの状況。
絶えず涙が溢れ、胴着を濡らす。
『俺はこのままココで死ぬんだ。寂しく死んでくんだ。ココで死んで、動物に食べられちまうんだ』
そう考えた瞬間、ゾクッと背筋が震えた。
『嫌だ、死にたくない。こんなとこで、死にたくない。俺は世界最強の剣士になるんだ』
涙を服の袖でゴシゴシ拭い、スクッと立ち上がった。
『とにかく歩くんだ。歩いてればきっとどっかに出れる』
そう力強く思い直し、左手の竹刀をぎゅっと握り締めた。
とりあえず、 こっちにまっすぐ歩いていこう、と道のない道をどんどんと進んでいく。
どれくらい歩いただろうか。真上にあった太陽は今は夕日に変わっている。
迷いなく歩き続け、ついに人がいるところまで来た。しかし、そこはシモツキとは違うところ。
「どこだ、ココ」
辺りをキョロキョロと見渡せば、いろんな店が出ている。
魚を売っている店、肉を売っている店、果物を売っている店、たくさんある。
シモツキ村の人間は基本自給自足だ。こんな華やかな店など見たことない。
どうやら森を抜け、反対側に出てしまったらしい。
それでも森の何もない場所に比べたらココは天国だ。人もいるし食べ物もある。
「ハラへった・・・」
あまりの空腹にフラフラと近くの果物を売っている店に近づく。
「いらっしゃい坊主。おつかいか?」
店の店主が気のいい笑顔で声をかけてくる。
ゾロは目の前の真っ赤なリンゴに目がいって離れない。
「あの・・・俺」
「ん?どうした?おつかいじゃねぇのか?」
「・・・あの」
ゾロはどうしようと考えていた。ついフラフラと来てしまったが、お金など持っていない。お金が無ければ、目の前に広がるリンゴやバナナ、オレンジなど買えやしない。
どうしよう、ハラへった、どうしよう、と考えていると、1人の子供の声が隣から聞こえてきた。
「おじさん、このリンゴ、6ケースください」
「はいよ、サンちゃんおつかいかい?偉いなぁ」
「おつかいとか言うな!仕事だ!」
「あぁ悪い悪い、お仕事感心だなぁ」
「・・・なんかバカにされてる気がする」
「あはは、そんなんじゃないよ。6ケースだったね。あとでお店に運んでおくよ」
「うん、お願いします。はい、これお金」
「はい毎度。じゃあね、気をつけて帰るんだよ」
「子供扱いすんな!」
ゾロは店主と隣の子供のやり取りを呆然と見ていた。
自分は無一文でリンゴ1つ買えないのに、この子供は6ケースも簡単に買ってしまった。
ぎゅるるるる〜
そんな時、またも腹の虫が盛大な音を立てた。
「んん?」
あまりの大きな音に、隣の子供がゾロの方を見た。
『うわっ、キラキラ』
それまで空腹すぎて外見など気にとめていなかったゾロは、子供の髪色に驚いた。
金色。キラキラしてる金色。シモツキにはこんなキラキラしたのいない。初めて見る金髪に目を反らせないでいると、グワッと子供がゾロを覗きこんだ。
「っ!?」
「おいってば!何度も呼んでるのに聞こえないのか?耳悪いのか?口聞けないのか?」
あまりにも見惚れていたらしく、 全く声が聞こえていなかったらしい。子供は頬をプクッと膨らませている。
「あ・・・いや、悪い、な、なんだ?」
少々緊張しながら返事をすると、なんだ喋れるんじゃねぇか、とブツブツ言っている。
「お前、ハラ減ってんだろ?俺んち来いよ、何か食わせてやるからさ」
「え・・・い、いいのか?」
「いいさ。俺んちレストランしてんだ」
「・・・・・・」
「どうした?来ないのか?」
「・・・・・・」
何も言わないゾロに、子供はいぶかしむが、すぐにあぁ、と手をポンと叩き、笑顔を向けた。
「平気だ、金ならいらねぇ」
「え・・・ほんとに?」
「ほんとだ!ハラ減ってる奴に食わせてやるだけだ。な、来いよ」
「・・・行く」
よし、じゃ早く帰るぞと、ゾロの手を取って子供は走り出す。急に手を繋がれたゾロはちょっと恥ずかしかったが、子供があまりにも綺麗に笑うから、その手を離そうとはしなかった。
子供に手を引っ張られるまま着いた所は、大きな魚の形をした大きな真っ白の船。
上の方になにやら文字を書いているが、あいにくゾロにはその字は読めない。子供がレストランだと言っていたから、 おそらく店の名前だろうということは分かった。
子供は手を繋いだまま船に乗り込み、店の扉を開く。
開かれたそこには、たくさんのテーブルがあり、今は休憩中なのだろう、客は1人もいない。
「ちょっとココで待ってろよ」
繋いだ手を離し、子供は店の奥へと消えていった。
ゾロは椅子に座るどころか、立っているのがやっとだった。
こんな華やかで綺麗で眩しい所になど、来たことないのだから。
子供が消えていったときの格好のままでいると、奥から子供とものすごく長く白い帽子を被った初老の男が現れた。
「あ、なんだよ座ってればいいのに。じじぃ、コイツだよ。ハラ減らしてるみたいなんだ、何か作ってやってくれよ」
「・・・あの」
「坊主、どっから来た?ここいらじゃ見ねぇ服装だな」
鼻の下で伸ばされた髭を2つの三つ編みにしている男が、子供のじぃさんで、このレストランの店主ということは分かった。
「俺、シモツキ村から来たんだ」
「シモツキっつうと、森の反対にある村だな。どうやって来た、1人か?」
「あ、いや、その、森で修行してたら迷って、ココに来たんだ」
「修行?」
「俺、世界最強の剣士になるのが夢なんだ」
「ほぅ、それでその竹刀か」
じぃさんはゾロが握りしめている竹刀を見た。そして三つ編み髭をフルンと震わせた。
「坊主、何が食べたい」
「え・・・お、俺、こんな綺麗なとこ来たことないから、よく分かんねぇ」
「そうか。好き嫌いはあるか?」
「ねぇ!なんでも好きだ!」
「よし、じゃ待ってろよ。すぐに作ってきてやる」
「いいのか!?ありがとう!恩にきる!」
「ははは、武士みてぇな坊主だな。チビナス、てめぇは坊主と一緒に待ってろ」
「チビナスじゃねぇ!」
聞けよ!とチビナスと呼ばれた子供は叫ぶが、男は素知らぬ顔でまた奥へと消えた。
もぅチビナスじゃねぇのに、とプンスカしながら、ゾロに座れよ、と椅子を引いてくれた。
ゾロはその椅子にそぅっと座ると、子供も隣の椅子にぴょんと座った。
「じじぃの作るメシは美味しいんだ!世界一だ!」
「世界一か」
「あぁ!世界一美味しいんだ!俺もいつかじじぃみたいなコックになるんだ!お前は世界一の剣士になるんだろ?同じだな!」
ニコニコ笑いながらゾロに話をする子供は、それはもぅ眩しいくらいで、なぜかゾロはまっすぐ子供の顔を見れない。
果物屋でもそうだったが、この子供はキラキラ輝いて見えて、ゾロは心臓がドキドキするのが不思議だった。
今までこんな風に顔をまっすぐ見れなかったり、心臓がドキドキすることもなかった。
そんなに緊張しているのかと、ドキドキしているのがバレないように、下を向いているのがやっとだ。
そうこうしていると、奥から男が両手に料理を乗せて現れた。
ゾロたちのテーブルまで来ると、前にスッと黄色い塊が置かれた。
『なんだ、これ・・・?』
こんな料理見たことない。かろうじて黄色が卵だろうとは予想がつく。黄色い塊の皿の横にスプーンが置かれ、それですくって食べるものだとは分かったが、この塊が何なのか分からない。
じっと塊を見ていると、男がオムライスだ、と言った。
「・・・おむらいす」
口の中で呟くようにして、スプーンを持って塊にさしてみた。すると、トロッと卵が溶けて中には赤茶色のゴハンが見える。
それをスプーンですくって、口に運んだ。
「・・・うまい!なんだこれ、うまい!」
そう言ったきり、夢中になっておむらいすを食べた。
掻き込むように食べ続けるゾロを、子供も男も微笑ましく眺めた。
「ほら、スープも飲め」
そう言われ、おむらいすの横に置かれたスープも飲む。これも驚くほど美味しくて、一気に飲み干した。
「ごちそうさまでした!」
無我夢中で食べ終わり、皿も舐めつくした。
パンッと両手を合わせ大きな声で言うと。
「じぃさん凄ぇな、ほんとに世界一なんだな。すっげぇ旨かった。俺、こんな旨いメシ食べたの初めてだ!ありがとう!」
椅子から降りて立ち、大きくお辞儀をするゾロに、男は目を細めると、今日はこのまま泊まっていけと進めてきた。最初こそ、そこまでしてもらうわけにはいかない、と断ったが、子供にも泊まっていけよと言われ、ありがたく受けることにした。
風呂にも入れてもらい、パジャマは子供が貸してくれたのを着た。
「よし、サイズもピッタリだな」
「・・・あひる」
「可愛いだろ、俺のお気に入りだ」
ゾロは黄色い服にアヒルのイラストがプリントされたパジャマ。目の前で満面の笑顔を浮かべる子供は、青い服にヒヨコが描かれているパジャマ。
イラストこそ違うが、お揃いのようなパジャマは気恥ずかしくも何故か嬉しくも思える。
子供はパジャマとお揃いの帽子を被ると、ベッドへと入る。
「ほら、お前も早く入れよ」
布団を捲ってゾロを呼ぶので、そろそろと布団の中に入った。
干したばかりなのか、太陽のいい匂いがする。
「おやすみ〜」
「おやすみ」
目を閉じると、布団の匂いと歩き回った疲れとですぐに眠りに就いた。
ゆさゆさ揺られる感覚に目を覚ますと、子供がゾロを揺すっていた。
「起きろよ、朝メシだぞ」
服を着替えて顔を洗い子供について行くと、オニギリと味噌汁の匂いがする。
「シモツキなら朝メシはコレだろうと思ってな」
男が薦める味噌汁を飲むと、これもまた美味しくて、旨い!と言ったきりガツガツ食べた。
「食べたら坊主を家まで送って行ってやるからな」
「何から何までほんとにすまねぇ。この恩は一生忘れねぇ」
深々と頭をさげるゾロの頭に優しく手を置き、気にするなと撫でられた。
昼過ぎにはシモツキ村に着き、ゾロの帰りを外で待っていた両親が男に礼を言い、子供と男はそのまま立ち去ろうとした。
それをゾロは呼び止めた。
「また、会えるか?」
子供はん〜、と考えるようにして口を開いた。
「俺たちのレストランは船だから、いろんな場所に行くんだ。だからもしかしたらもう会えないかもしれない」
その言葉を聞いて、ゾロは竹刀を持つ手にぎゅっと力を入れた。
子供はそのあと、でも、と続ける。
「でも、もし、もしまた会えたら、その時は、俺がじじぃよりも美味しいメシを食わせてやるからな。だから、また会おう!」
元気でな、と子供と男は帰って行った。
2人の姿が小さくなった頃、子供が大きな声で叫んだ。
「忘れるなよ!俺たちのレストランの名は、海上レストラン・バラティエだ!」
シュッと風を切る音がして、バチッと目が覚め、風を切ったモノを刀で受け止める。
「やっとお目覚めか、マリモくん。朝メシだ」
「もっとまともに起こせねぇのか」
「そうしてほしけりゃ声かけた時点で起きるんだな」
ニヒルな笑みを浮かべ、刀で受け止められた脚を下ろし、クルッと踵を返し、カツカツと音をさせてキッチンへと歩いていく後ろ姿。
あの日、ルフィたちと訪れた魚の店でアイツに会ったとき、すぐにあの時の子供だと気づいた。
店でゼフと目が合ったとき、右手を掲げて見せたから、ゼフは俺を覚えていたのだろうが、あいにくアイツは覚えていないようだった。というか、ナミしか見ていなかった、という方が正しいかもしれないが。
「ったく、忘れるなよって言った本人が忘れてんじゃねぇよ」
だからお前はアホアヒルなんだ、と口には出さずに心の中で愚痴る。
俺はお前のことを忘れたことなどなかった。いつか、必ず会ってやると思っていた。
『いつか、また会えたら、その時は・・・』
昔聞かされた言葉が今でも鮮明に思い出される。
「旨いメシ、食わせてもらってるよ」
いつかアイツに昔話をしてやろう。アイツは本当に覚えていないかもしれないが、それでもいい。その時は、あの時言えなかった俺の想いも全部、ぶちまけてやろう。
クスリと1つ笑いをこぼし、キッチンへと歩き始めた。
『また会えたら、その時は、ありったけの想いを込めて、お前に好きだと告げるよ』
END
相互記念として、晴稀さんからいただいてしまいましたー!
子ゾロが可愛い〜v
天然迷子癖で、礼儀正しくて義理堅いんですよね子ゾロは昔から!
そしてちびなすがとっても元気。
きらっきらした髪と笑顔で、お使いに行っても人気者なんだろうなあ。
本当は出会っていた二人。
サンジは覚えていないのか、本当は覚えていて黙っているのか。
どちらでもいいと、ゾロは思ってるはずです。
だってゾロの想いは揺るがないもの。
ゾロの告白を受けてサンジがどんな顔をするのか、想像するだけでニヤニヤしてしまいました。
可愛くて微笑ましい、けど現在にきっちり通じる幸せSSをありがとうございます!