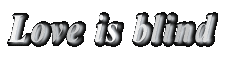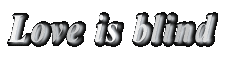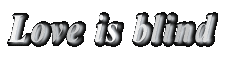なぜなんだ・・・?
理由を考えても分からない。
闇の中で規則的に響く音が耳に張り付く。
ギシギシと軋む音。
縛られた手首は擦れてくい込み、痛みが増す。
そんな痛みよりも、中に埋め込まれるモノの熱さに気が狂いそうだった。
抵抗出来ない事を刻み付けられ、内側から熱に犯される。
身体も心も全てを奪われる恐怖が、この部屋を支配した。
この繰り返される行為に、何の意味があるのかわからない。
ただ支配され、与えられるものを受け入れるしかない自分の無力さに打ちのめされる。
それでも抵抗し、全てねじ伏せられる。
節操なく身体が覚えた快楽を求める。
心を裏切り、身体は簡単に堕ちていく。
助けを求めて腕を伸ばすと、がっちりした身体がある。
縛られた腕で無我夢中で縋った。
―――だが、縋った相手に堕される。
「っ、ん…っ…ああっ」
揺さぶられ喘ぎ続けた喉から引きつった声がこぼれる。
サンジは潤んだ瞳を開くが、視線の先には闇が広がっていた。
ここには一筋の光もない。
サンジは目隠しをされていると自覚しながらもそれを取ることはできない。
何故こんな事になってしまったのか全くわからない。
必死で記憶を整理しようとするが、それを邪魔するかのように揺さぶられた。
中から脳へと伝わる快感に、声が止まらない。
自分のものとは思えない声が響きわたった。
現実から逃げたくても、逃げられない。
涙は止めどなく流れ、絶望に支配された心は悲鳴を上げ、壊れそうだ。
狂えたなら、どんなに楽だろう…。
―――だけど、まだ、狂えない。
サンジは与えられる快楽の強さに泣く事しかできなかった。
あの日サンジはいつものように図書館に向かった。
シーンと静まり返っている図書館のドアを静かに明けて入り、室内を見回す。
窓際で静かに本に目を落とす人物を見つめながら、サンジはゆっくり彼に近づいた。
彼はサンジが通う学校の先輩で、ロロノア・ゾロ。
一つ上の兄、エースの親友だ。
ゾロの傍に着くとサンジは小さな声で呼びかける。
「ゾロ」
本に向けていた顔をゆっくり上げ、少しも笑わずサンジに視線を向けた。
「…今日は早いな」
「そうか?」
愛想笑いも何もないゾロの態度を気にもせず、サンジは笑う。
「今日は何を読んでるんだ?」
興味をもち本を覗き込む。
「ひとつなぎの大秘宝」
「いつも難しい本読んでるよな」
「そうでもない」
嫌みではなく、淡々とゾロは答える。
表情を一切浮かべないゾロの顔は整っていて、冷たい印章を与える。
涼し気な瞳はサンジを無視して、本に戻った。
ゾロはいつもこんな感じなので気にせずに話しかける。
「兄貴からの伝言。今日は遅くなるから先に帰ってくれってさ」
エースの使い走りをいつもしているサンジは、今日もゾロに伝えた。
それはサンジがこの学校に入学してから習慣になっていた。
最初は敬語だったのだがいつの間にか敬語を使わず話すようになった。
「そうか」
ゾロは視線を本に向けたま返事する。
「じゃゾロ、伝えたからな」
「なあ」
歩き出していたサンジは声をかけられ驚いて振り返る。
「どうしたんだ?」
驚いたサンジがゾロを見ると、眉を少し顰めた。
「何故、いつもエースの使い走りをしているんだ?」
何かあるたびサンジはエースに使われている。
自分に関しては今まで全く興味を示さなかったゾロの突然の問いかけに、サンジは大きめの瞳を輝かせた。
「何でって、ん?…多分、オレ兄貴が好きだからかな。それに人に何か頼まれるの好きだし。好きでやってるのと
変わらないだろ」
あっけらかんと笑って言うサンジに、ゾロの呆れた瞳が向けられる。
「ブラコン」
「ははは。そうだな」
そう笑い飛ばして、サンジは愛想よく手を振って図書館を後にした。
サンジにとってエースは自慢の兄だ。
勉強もスポーツも出来る。
人望は厚いし、誰に対しても優しい。
もちろん、自分に対してもそうだ。
疲れていても頼めば勉強を見てくれるし、他にも言い切れないくらいサンジはエースに甘やかせてもらっている。
それを思えば、使い走りなど気にもならない。
それ以上にエースの役に立つのであれば、幾らでも何かをしてあげたい。
それをブラコンと言われるならそうだとサンジは自覚しているし、自他共に認めているので今更の事だった。
サンジが歩く廊下を夕日が赤く染めている。
生徒会室のドアをノックすれば、自慢の兄が顔をのぞかせた。
「お、サンジ」
自分に笑いかけるサンジにエースは微笑み、その頭に手を置いた。
ポンポンと軽く叩いた後に柔らかな髪を掻き混ぜた。
「今日はもう用はない?」
エースの手を払いのけることなく無邪気に笑いながらサンジはエースを見る。
少し悩んでから、エースは言いにくそうに、
「えっと、…ロビンにも、先に帰るように伝えてくれないか?」
ロビンというのはエースの彼女だ。
自慢の兄には相応しくとても綺麗で、家にも何度か遊びに来ていた。
サンジは二人の中を祝福し、応援していた。
「ロビンちゃんには、自分で行った方がいいよ」
「でもな…」
「そーいうのを大切にしないと、ダメなんじゃないの?ロビンちゃんが可愛そうだよ」
“女の子は大切に”という考えのサンジらしい言葉に苦笑して頷いた。
「そうだな。じゃ、遅くなることだけ伝えてくれるか?それで、もし待てないようなら帰ってもいいと、言ってくれるか?」
「わかった。でもロビンちゃんのことだから、待ってくれるよ」
明るく笑うサンジに、エースは感謝しながら頷く。
「じゃ、頼むな」
「うん、じゃ」
真っ直ぐに走って行ったサンジの後ろ姿をエースは見送った。
ロビンのいる教室を目指し、一段とばしながら階段を上がる。
二階の廊下を走り、教室を覗く。
ロビンは誰もいない教室で一人座って本を読んでいた。
「ろーびーんーちゃ?ん」
その姿を見つけるとすぐに声をかけた。
ロビンの綺麗な黒髪が振り向いた瞬間にさらりと広がり、サンジに微笑む。
「あらサンジ君。伝言かしら…?」
「そう、ロビンちゃん」
「いつもありがとう」
「いいえ、好きでやってるから。遅くなるから、ってさ」
「そう。いつものことだけど…」
寂し気に微笑むロビンにサンジはにっこりと笑う。
「あのさ、ロビンちゃん。ここだけの話だよ。兄貴はすっごくロビンちゃんのこと好きだよ。いつも自慢してるんだから、
大丈夫だよ。安心して」
寂し気だった表情が明るくなる。
「あんまり遅くて待てなかったら、帰っていいって言ってたけど、ロビンちゃんは待つよね?」
「…そうね」
「そう言うと思ったから、待ってるよって言っといたからね?」
「サンジ君は本当によく分かってるわね。ありがとう」
クスクス笑いながら、元気が戻ったロビンを見てサンジはほっと安心する。
「そろそろオレ帰らないと」
「ええ、またね。気をつけて」
「もう子供じゃないよ!じゃね。バイバイ」
笑って教室を出たサンジは、階段を駆け下りる。
一階に着き、廊下を曲がった瞬間、ドンと誰かにぶつかりサンジは後ろに弾かれた。
そのまま後ろにこけそうになるサンジの腕を、誰かが咄嗟に掴む。
「…うわっ!」
ガシッと大きな手に力強く掴まれ引き寄せられたサンジの身体は、誰かにしっかりと抱きしめられた。
一瞬の出来事に思考が停止し、サンジは動けずにいた。
「大丈夫か?」
聞き覚えのある声に顔を上げれば、相変わらず無表情のゾロがいた。
「あ、ああ。大丈夫…って、わるい!ゾロの方こそ大丈夫?」
まだ抱きしめられている状態に慌てて、急いでゾロから離れる。
「オレは大丈夫だ。気をつけろ」
冷たい口調のゾロを全く気にせずに、サンジは素直に頷く。
「…ごめんな。気をつけるよ」
「また、エースの用事か?」
「そうだけど、もう終わったから帰るところ」
嬉しそうに言うサンジを眉間に皺をよせゾロは見ている。
「そうか」
サンジはそんな事を気にすることはなく、不思議そうにゾロを見た。
「ゾロも今帰り?」
「ああ…そうだ」
「じゃ、一緒に帰る?」
笑顔でゾロに聞くが、ゾロは答えない。
「……いい、遠慮する」
少し沈黙した後、無表情で断るゾロに、サンジは頷いた。
「あっそう、じゃあまた」
「……」
返事のないゾロを気にせずサンジは走り出した。
靴を履き替え、校門を出る頃には辺りはすっかりと暗くなっていた。
冷たい風を感じながら、サンジはぼんやりと誰もいない公園のブランコに腰掛けた。
何気にブランコを揺らせば、夕闇の中にキィキィと響く。
星もない空を眺めて、サンジは悲しげに眉を寄せた。
「ブラコン…か。…まあ、そうなんだけど……な」
小さな声で呟き、サンジは俯いた。
サンジは自嘲気味に笑い、その笑みは普段とは違い酷く悲しげだった。
俯いたサンジの瞳にじわりと涙が滲む。
どうしても、言えない思いがここにある。
誰にも言えない秘密を抱え、サンジは悲しみを抑える。
「うっ…ひっく」
けれど抑えきれない思いが嗚咽と共に涙となって溢れる。
いっそ、伝えられたなら。
何度も思う。
だけど…言える訳がない。
伝えたい言葉を、何度も何度も飲み込んだ。
涙が頬を伝って流れる。
サンジは涙を拭うことなく流し続けた。
近くからジャリっと乾いた土を踏みしめる音が聞こえ、サンジは奥歯を噛んで嗚咽を抑える。
きっと通行人だろう。
サンジには通行人を気にする余裕などない。
ただ、嗚咽を抑えることしか出来なかったのだ。
一度溢れ出た悲しみは次から次へと溢れる。
直ぐ傍に近づいてくる足音にすら気付かず、サンジは泣きつづけた。
俯くサンジの視界の隅に、誰かの足が映った。
「…?」
ぼやけている目を擦り、サンジはゆっくり顔を上げる。
暗くなった公園でサンジの前に立っていたのはゾロだった。
ゾロの姿にサンジは驚き言葉をなくす。
「…酷い顔だな」
淡々とした口調のゾロは、サンジを静かに見下ろしていた。
「ゾ…ロ……タイミング悪いって」
目元を慌てて擦り呟きながらサンジは笑ってみせるが、その笑みは一瞬で消えた。
サンジの瞳からは涙がボロボロとこぼれた。
「フッ…ハハ…、兄貴には言わないでくれよ。心配…する…から」
溢れる涙を隠すように俯き、サンジは明るい声で必死にゾロに告げた。
ゾロはそれを見下ろしながら、眉間に皺を寄せて低く答えた。
「…わかった。それでお前はそのままで帰れるのか?」
「大丈夫…だいじょ…ぶ…だいっ…じょ…ぶ…だか…ら」
サンジの声は嗚咽で途切れた。
そのまま言葉を続けられないサンジは、唇を噛み締め嗚咽を噛み殺す。
涙を拭うため必死で目元を擦るサンジの手を無言でゾロは掴む。
「…ッ??」
手を突然掴まれ、驚いたサンジがゾロを見ると、ゾロは短く息を吐いた。
「…来い」
「えっ…?」
「いいから黙ってついてこい」
突然言われた言葉に返答出来ず、呆然とゾロを見つめた。
手はしっかりと掴まれ離してもらえそうにない。
サンジは困惑の表情を浮かべたまま、無言でついて行くしかなかった。
連れて来られたのはゾロの住んでいるマンションだった。
広いその部屋は物が極端に少なく、生活感がまるでなかった。
自分の部屋と違いサンジは落ち着かなかった。
リビングにサンジを残し。ゾロは奥の部屋に入った。
部屋を見回し、まだ霞む視界を擦った。
「手で擦るな」
背後から聞こえてきた声にビクリとなりながらサンジは振り返った。
黒のシャツにジーパンという普段着に着替えたゾロがコーヒーカップを手に、無表情でソファーに座るサンジを
見下ろしていた。
「ゾロ…ほんと、ごめんな」
少し落ち着いたサンジは掠れた声で呟く。
その表情にいつもの明るさはなかった。
「…落ち着いたか?」
少しだけ優しい声で聞かれサンジは小さく頷いた。
静かに自分の前に回り込んできたゾロに無言でカップを差し出され、サンジは躊躇しながら受け取った。
「…」
暖かく少し甘いコーヒーを飲むとサンジの悲しみは少し和らいだ。
そんなサンジを横目で確認するがゾロは何も話さない。
普段のゾロを知っているサンジは凄く不思議な気持ちになった。
サンジの知っているゾロは、本以外に興味を殆ど示さない。
日頃から物事に冷めたような視線と冷たく感じる口調で他人に構うような人ではなかった。
それが、今は自分をわざわざ自分の家に連れてきて、コーヒーまで出してくれている。
ぼーっとゾロを見ていたサンジは、視線が合うと気まずくなって顔を俯けての中で空になっているカップを持て余した。
「エースの事か?」
コトンとテーブルにゾロは持っていたカップを置く。
何を言っているのとサンジが顔を上げてゾロを見れば、無表情のゾロがじっとこちらを見ていた。
「え…?」
「お前が泣くんだからどうせエースの事なんだろう?」
冷たく責めるような口調で言われサンジは戸惑う。
「ゾ…ロ…!?」
ゾロは強い力でサンジの手首を掴み、空いている手で顎を掴む。
ゾロの強い眼光に囚われ、サンジは言葉を失い動く事も出来ない。
「エースが好きなんだろう?」
ゾロの言うそれはきっと家族としてという意味ではないだろう。
サンジはそれを直ぐに理解し、ゆっくり首を振った。
「―――…違う…」
「違わないだろ?なら何故泣いていた?」
「…」
その言葉に答えられず、サンジは唇を噛み黙る。
そして質問してきたゾロを真っ直ぐに見ると
「…言いたくない」
目の前のゾロにキッパリと答えた。
次の瞬間、サンジは唇に何かが触れる感触に驚き、限界まで瞳が開いた。
サンジの唇に重ねられているのはゾロの唇だった。
それが分かってもサンジは動けず、重なった唇を感じながら幾度か瞬いた。
長いのか短いのかわからない数秒が流れ、ゾロの唇が離れる。
同時に、愕然としているサンジの腕を掴み、頭上で戒める。
「えっ…何…っ」
咄嗟に反応出来ずに、少し遅れて抵抗する。
だがそんな抵抗は簡単に抑えられ、ゾロは無表情でサンジのズボンのベルトを引き抜くと腕を一つに縛った。
「痛ッ…やめっ…ゾロ、何を!?」
暴れようとするサンジを軽く抱き上げ、ゾロは何も言わないままリビングを出る。
奥の部屋に運ばれたサンジはベッドの上に投げ出された。
ギシッとサンジの重みでベッドが軋む。
「ゾロッ!?」
ゾロの意図が分からず訴えるようにサンジは激しく呼ぶがゾロは何も応えない。
ただじっとサンジを見つめているだけだ。
その瞳をサンジは見つめ返し、必死で感情を探ろうとする。
だが、何も読みとれない。
それは恐怖へとつながり、サンジは怯えた表情を浮かべた。
その表情を見て、フッとゾロが自嘲気味に笑う。
「…―――」
今の事態よりもゾロの笑みにサンジは驚いた。
今までゾロが笑っていることなど、サンジは見た事がなかった。
だがその驚きは長くは続かない。
サンジの視界はゾロの手によって閉ざされた。
「ちょっ!?止めッ…」
そして視界は布のような物で完全に閉ざされる。
拘束され、視界も奪われる恐怖にサンジは身を小さく強張らせた。
それからどれくらいの時間が過ぎたのだろう。
サンジはあのまま放置されていた。
この部屋にゾロがいるのかさえわからない。
この状態で待っていることも出来ずに、何度もゾロに呼びかけたが反応は全くない。
名前を呼ぶのも疲れた頃、サンジはベッドに寝転がっている身体をゆっくり動かした。
この状況から何とかして逃れようと腕のベルトを外そうと試みる。
しかしどうしても外れず皮膚を擦り傷つけるばかりだった。
ヒリヒリとした皮膚の痛みに眉を寄せる。
何か大きな勘違いをゾロはしている。
その確信を持ったサンジは、焦りどうにかしようともがく。
どうにか起き上がろうとしたサンジの首筋にひやりとした手のひらが触れた。
「ッ…」
突然の予期せぬ接触に、サンジの身体がびくりと強張る。
「―――ゾロ、話を…!」
必死で声を張り上げサンジが訴えるが、相変わらず返事はなかった。
代わりに首筋の冷たい手のひらが、ゆっくりと動く。
じっとりとした動きで首筋を撫で上げられ、サンジは息を飲んだ。
その手はそのまま頬へと上がり、手のひらが頬を掴んで僅かに上を向かせる。
無意識で薄く開いている唇にゾロの舌が押し付けられた。
口腔にぬるりとしたモノが入り込み、その感触にサンジは悲鳴を上げる。
「んっ…んんんんっ」
悲鳴はくぐもった声にしかならず息苦しさが増した。
捩じ込まれた舌先がサンジの口腔内を犯し、歯列をなぞる。
押し出そうと突き出した舌先を絡めとられ、軽く吸い上げられた。
「…んっ…ふ…っん…ぁ」
ぴちゃっと唾液が密かな音をたてサンジの背筋が震える。
腰の辺りからゾクゾクとした何かが這い上がり、じっとしていられずサンジは身体を捩った。
絡めとられた舌先は歯を甘く立てられ吸い上げられる。
伝わる粘膜の感触は生々しいのに嫌悪感はなかった。
それどころか、ジーンと頭の中から痺れるような甘さを覚えサンジは困惑した。
口腔を散々犯され、解放されたサンジは荒い呼吸を繰り返す。
「んっ…は…っ…」
サンジの息が整う間もなく手のひらが身体を撫でる。
薄い胸板を撫でられサンジは身体を捩って逃げようとした。
そんな小さな抵抗は何も防げず、ゾロの手はサンジのブレザーを肩からずりおろしシャツのボタンを外しているようだった。
「やめっ…」
冷たい空気が素肌につたわりサンジはシャツがはだけられた事を知る。
自分の白く痩せた肌を見られていると感じた瞬間、猛烈な羞恥がサンジの身体中に広がった。
羞恥に身体を震わせサンジは頭を振って懇願する。
「ゾロ……もう、止め…ひっ!?」
つーっと冷たい指先がサンジの脇腹をたどり、ゆっくりと胸の方へ上がる。
そしてサンジの胸の突起をゆっくりその指が押しつぶす。
「んんっ…あっ…ああ!」
そんな場所を弄くられ快感があると思わなかったサンジは声を漏らす。
甲高く甘い声にサンジはカアッと頬が赤くなる。
そのままクイッともう一度押しつぶされ、サンジは身体をくねらせ声を堪える。
「ん…」
きつく唇を噛み締めて耐えたサンジの突起をそのまま執拗に弄くられる。
指先で摘まれ、押しつぶされる。
繰り返し行われ、サンジは反応しないように必死で我慢した。
指の動きが止まりサンジがホッと息を抜いた瞬間、ぬるっとした何かがその突起に触れた。
「…ん…ぁっ…ああっ…嫌ぁ…」
きゅっと吸い上げられる快感に耐えきれずサンジは喘ぎ身体をくねらせる。
焼け付くような熱さが後を追ってそこから身体中へと広がってゆく。
そしてその熱は、腰へと溜まりじっとり疼く。
形を変えているであろうモノをゾロの手で撫で上げられサンジは喉を仰け反らせた。
熱を持って触れられるのを待ちわびていたペニスは硬く立ち上がっていた。
自分の意志に反して反応した身体をサンジは呪う。
ジジィっとジッパーを下げられる音に、サンジは表情を強張らせ力一杯喚いた。
「止めろ!嫌だ!止めろー!!」
暴れるサンジを冷たい手のひらが押さえつけ、ズボンと下着を一緒に引き下ろす。
冷たい空気にさらされたサンジのペニスは細かく震えた。
「…ひっ…やめっ…っく…」
それまで必死で抑えていた感情が押寄せ、サンジは涙を流す。
流した涙は目隠しに吸われ、声は羞恥に引きつっていた。
「どうして…こんな事…何の…意味…がっ…」
「―――意味なんて…ない」
今まで黙っていたゾロは口を開いた。
その声にサンジは少し安心した。
胸では不安が渦巻いていた。
もし今触っているのがゾロではなかったら…と。
そんな思いを押しのけサンジはゾロにどうにかちゃんと話がしたいと名前を呼ぶ。
「ゾロ…んん…ッ…う」
しかしそれは唇によって塞がれる。
暖かく優しい口づけは突如貪るようなものに変わった。
どちらのものかわからない唾液を飲み込み、サンジは荒い息を繰り返す。
ゾロの手が下に移動し、サンジは少し開いていた足を咄嗟に閉じる。
しかしそれよりも早く欲望はゾロの手に囚われ、強烈な快感が走った。
初めて他人に触れられたサンジは悲鳴に近い声を上げ、快楽に泣く。
既に濡れている先端をゾロの指がクッと押す。
たったそれだけで一気に上り詰めそうになったサンジはビクンと身体を跳ねさせた。
「止めッ…離…せ、触っ…る…な…ぁぁっ」
サンジの声は言葉とは裏腹に甘い。
そんなサンジの耳たぶに唇を寄せてゾロは呟いた。
「いやらしいな。こんなに濡らして…エースにも弄ってもらったのか?」
「兄…貴は…関係な…っ、んん」
必死で否定しようとしても声は喘ぎに変わってしまう。
「本当は、エースにこしして欲しいんだろ?」
「違う…っ、違っ…ああっ…」
かりっと甘く耳たぶを噛まれ、甘美な快楽と同時に告げられる言葉は酷くサンジを傷つける。
「やめっ…もう…ダメッ、離せ…っ…あああぁっ」
限界まで身体を強張らせサンジは我慢出来ずに白濁の欲望をゾロの手に放つ。
放ったと同時に訪れる開放感と虚脱感、そして、猛烈な羞恥が入り混じりながらサンジはぐったりとベッドに沈んだ。
荒い呼吸を繰り返しているサンジは、足を掴まれ開かされ、身体を強張られた。
そっと何の前触れもなく後ろを触られ、サンジは声を上げる。
「ヒッ…!?」
自分の放った液体で濡れているらしい指先が、ソコを幾度も擦り始めた。
「えっ…何ッ?あ、嫌、だ…」
信じられないと恐怖で暴れるサンジに構う事なく、指はアナルを弄りつづける。
幾度も弄られ少しずつ緩んできたソコが次第にヒクツキはじめる。
それを自覚してサンジは一層抵抗するが、力の入らない身体では大きな抵抗にはならなかった。
ゆっくりと、指が内部に入ってくる。
「―――ッ!あっ…やぁ…ひ…っ…」
そして指が奥まで押し込まれ、ぐっと内壁を擦った。
裏返った声を上げ、サンジは目隠しの下で涙を流す。
今までに感じた事のない快感がアナルを擦られるだけで込み上がってくる。
痛みは殆どなく、ただ強烈な快楽を与えられる。
泣きながらサンジは指を止めてくれと懇願する。
だがそれにゾロはあやすような口づけをサンジに与えるだけで決して止めてはくれない。
内側から湧き上がる快楽は本当に恐ろしいものだった。
自分の中身を全て暴かれているようで、サンジはなり振り構わず懇願だけを繰り返した。
「止めて…くれ…もう…ああっ…ゾ…ロ」
首を振り、上手く発せない言葉を必死で叫ぶ。
いつのまにかアナルに入れられている指は増え、内壁を幾度も強く擦り上げられている。
その度に身体をよがらせ、声を漏らし、サンジは解放を願う。
それが伝わったように内壁からチュクっと微かな音を響かせ指が引き抜かれた。
ほっとすると同時に内壁が疼くような感覚を認めたくなくてサンジは唇を噛んだ。
乱れた息を整えようと浅い呼吸を繰り返すサンジは、アナルに熱い塊を押し付けられ、身体が強張る。
多分、それは…ゾロの…。
こんな形で、その行為を受け入れられるはずがなかった。
サンジは必死に逃げ惑い、身を捩りずり上がる。
その細い腰をゾロが掴むと、ゆっくり入口にゾロのペニスが押し付けられた。
「嫌…だ、…ゾロ…こんな…止めろ…っ」
もう逃げられないのはわかっていた。
それでも訴えられずにはいられない。
「エースの名前を呼べばいい…オレはそれでも構わない」
静かな囁きと共に、ぐっと先端が内部へと進む。
熱い塊がサンジの中をゆっくりと進んでくる。
「や、ぁ、あっ…あああっ!!」
ゆっくりと半分まで埋め込まれ、後は一気に貫かれた。
引き裂かれそうな痛みとそれ以上の快感が内部から広がる。
後はもう、何もかもが分からなくなるほど、サンジは揺さぶられた。
ふっと瞳を開ければ、闇が広がっていた。
まだ目隠しされているのだと思ったサンジは手が自由にならないかと動かしてみる。
縛られていた腕が自由になっていたので、目隠しを外そうとした。
だがそこには布はなく、目に触れても何もなかった。
ああ…真夜中…なのか。
ぼんやりと思いながらサンジは上半身を起こす。
同時に、中から何かが溢れ出すのを感じ身を強張らせた。
「っ…う…ん」
散々ゾロのペニスをくわえた場所がほころび、流し込まれた体液が溢れる。
その感覚は堪え難く、サンジは引きつった声を漏らした。
細かく背が震え、サンジは身体に力を入れないように小さな呼吸を繰り返す。
闇の中でその感覚が収まるのを待ったサンジは、小さく声を出した。
「ゾロ…?」
喘ぎ、泣き続けた結果、酷く掠れたサンジの声が闇に響く。
「…気がついたのか」
すぐに返された声はサンジの居るベッドの足元で響いた。
声がした方向に視線を向け、サンジは唇を噛み締める。
「何で…!!なんで、こんな…」
そこにゾロがいると分かった途端、サンジは強く叫んだ。
そして同時に涙が零れる。
伝えたい事は山ほどあった。
だが、言葉は出て来ない。
悔しさともどかしさにサンジが嗚咽を漏らす声がしばらく響いた。
「…許してもらおうとは、思っていない」
相変わらず淡々とした声と闇のせいで、サンジにはゾロがどんな顔をしているのかわからない。
ゾロのいる方向を睨んでサンジは続く言葉を待つ。
「…」
「憎みたいなら、憎めばいい…」
「何で、そんな…一方的なんだ!?」
冷めた口調で呟くゾロにサンジは強く言い放つ。
そしてサンジは意を決し、唇を噛み締めた。
「どうして、オレの話…聞いてくれなかったんだ?」
「聞く必要はない」
「そうか。じゃあ、オレも勝手に話すから!」
いつまでも一方的な会話にサンジは苛立言い切る。
「オレは、別に兄貴が好きな訳じゃない。…好きな人は別にいる。いつも黙ってて何考えてんのか分からない
奴だけど…好きなんだ」
―――確かに兄貴は好きだ。
だけどそれは恋愛感情としてではない。
明らかに違うとわかっていた。
そして、自分が恋してる相手はゾロだった。
男に恋した自分を認められず、何度も諦めようとした。
けれど、自分の胸を動かすのは、素っ気ないその男だけだった。
兄を恋愛感情の対象としていると勘違いされ、その挙句犯されてしまった自分が不憫でならない。
公園で泣いていたのも、決死の思いで一緒に帰ろうと誘ったにも関わらず、断られたからだった。
泣いていた原因を聞かれて、ゾロだなんて言える訳がない。
「待て…話が見えない」
天然なのかバカなのか、どちらにせよ鈍い事に変わりはない。
サンジは涙で潤んだ瞳でゾロがいるであろう場所を見つづけた。
「ゾロが好きだって、言ってるんだよ」
こうなった以上、開き直るしかない。
散々好き勝手されたのだから、もうどうなってもいいとサンジは思った。
しばらく続く沈黙をサンジはイライラしながら待っていたが、痺れを切らしてゾロに訴える。
「…電気、付けてくれよ」
「今は、待ってくれ」
そう告げるとゾロが動く気配がした。
その次の瞬間、サンジはゾロの腕の中に抱きしめられる。
ぎゅっと強く抱きしめられる感覚に、ようやく安堵が広がった。
泣きたいような気持ちを押さえつけて、サンジはそっと手をのばす。
闇の中で見えないゾロの頬を手で包み、サンジは唇を押し付ける。
触れるだけの口づけをし、ゾロの胸に甘えたサンジは静かに問う。
「なあ、ゾロ。どうして、オレにこんなことしたんだ?」
「…それは…同じ、気持ちだったから。誰にも渡したくなかった。お前以外何も見えなかった」
動揺を滲ませた声で低く呟いたゾロに、サンジは小さく笑う。
追求も、謝罪も、させたいことは多々あったが、サンジは許す事にした。
「これからは、サンジって呼んでも…いいか?」
不器用に問いかけてくるゾロにサンジは綺麗に微笑み頷いた。
ゾロの唇がサンジのそれに重なる。
それは愛のある暖かく優しいものだった。
END