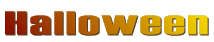「Trick or treat!」
扉が開くと同時に、可愛らしい声が足元から飛んできた。
サンジは咥え煙草のまま振り返り、にかりと笑う。
「おうおう、随分早起きだな」
そう言ってまだ温かいクッキーを紙に包むと、手早くリボンをかけてやる。
「ほい、悪戯は勘弁な」
全身に白いシーツを被っただけの小さなモンスターは、シーツ越しに両手を差し出しクッキーを受け取ると、
弾むようにラウンジの外へと出て行った。
「さって、そろそろみんな起き出す頃かなあ」
朝靄に煙る海は凪いでいる。
今日もいい天気になりそうだ。
「Trick or treat!」
「うわあ、可愛い〜んvv」
みかん畑からぴょこんと顔を出してきたナミに、サンジは万歳しながら身をくねらせた。
「なんって可愛いんだナミさん!黒猫耳がすごくすごく似合ってるよううう!」
「うふ、そう?」
サンジの褒め言葉に気をよくして、ナミはくるりと背を向けた。
短いスカートの下からくるんと巻いた尻尾が覗いている。
「し、尻尾・・・かはっ」
うっかり吐血しそうになって、サンジは慌てて口元を抑えた。
だが鼻からはダラダラと鼻血が流れ出ている。
「うんもう、だからTrick or treat?」
「ひゅいいん、ナミひゃんになら悪戯されたい〜〜〜」
だらしなくその場で膝を着いたサンジから有無を言わさずお菓子を取り上げ、ナミは颯爽と立ち去った。
「それって強奪じゃねえの」
半ば呆れてその光景を眺めていた全身南瓜色タイツのウソップが、サンジの顔を引き上げてティッシュを当ててやる。
「ああ〜ナミしゃん可愛すぎるって罪だ〜〜」
「はいはい、ところでTrick or treat?」
改めてウソップに視線を移しあからさまにげんなりとした顔をして、サンジはポケットから菓子を取り出し無造作に渡した。
「Trick or treat!」
物陰からいきなり現れたのはフランケンシュタインだ。
むしろそのまんまで、仮装しているとは言えない出来で違和感すらない。
「おらよ」
「お前本当に、男には素っ気無いな」
それでもコーラ味の菓子詰め合わせを貰って、フランキーは子どものようにはしゃいでいる。
「Trick or treat〜!」
これぞそのまんまな骸骨紳士が、シルクハットを片手に恭しくお辞儀をしてきた。
「いや〜懐かしいですねえ。若い頃はこうして怪しげな装いで街へ繰り出して夜中遊んだものです」
「今年は生憎、船の上だがな」
「いえいえ、船の上でもとても賑やかで楽しいですよ。なんせお嬢様方がまた華やかで麗しい〜v」
「だよなーっ」
途端に意気投合して、二人で顔付き合わせ身体をくねらせる。
「普段から美しいレディをよりゴージャスに装わせてくれるよな、仮装ってやつは!」
「その通りです、元々お祭りごとが好きで血沸き肉踊るんですけどーっていうか、私血も肉ももうないんですけどホホ〜」
「ハロウィンだけじゃなく、クリスマスも正月もこれからずっと俺らで祝うんだぜ」
サンジの言葉にブルックは少しだけ目を(眼窩を?)瞠って、それから零れるような笑みを浮かべた(・・・ように見えた)。
「はい、あなた方に出会えてこの船に乗って、今年からはずっとですね」
「そうさ、ずっとだ。一人きりじゃねえ、みんなで祝う」
「はい、みんなで!そのためにも私は張り切って、骨身を惜しまず悪霊どもを脅しまわります!骨はともかく身は
もうないんですけどヨホホ〜」
軽い身のこなしでくるりと回転し、サンジの手から菓子を取り去ってマストを登った。
彼がああして周囲を脅してくれるなら、蘇る死者も恐れをなしてこの船には近付くまい。
「Trick or treat!」
気配で予測してサンジは身構え、飛んできた船長を軽く蹴り飛ばしてから用意していた大袋を抱えた。
「サンジーおやつーっ」
腕を伸ばしてマストを掴み、蹴り飛ばされた反動を利用して再度突っ込んでくるルフィを寸前でかわして甲板に沈めた。
フランキーから文句が出るだろうが、サンジのせいではない。
「まあ落ち着けくそゴム、ほらお菓子」
砕けた床から苦労して頭を抜いたルフィは、ぶんぶんと首を振って木切れを払った。
頭に飾った小さな角は外れていない。
「おう、んじゃ悪戯しねえぞ!」
「お前の場合は盗み食いだ」
にやりと笑いながら大袋を投げれば、ルフィは両手で抱えて嬉しそうに飛び跳ねた。
「俺のお菓子だな」
「おう、おやつは別に用意してあっから、それは自分用で大事に食えよ」
「ししし、ありがとうよサンジ!」
赤いシャツのゴブリンがご機嫌で駆けていく。
今日は仲間たちが順繰りにお菓子をねだりに来るから、何かと忙しい。
サンジとて、そのつもりで銘々の分をちゃんと用意してあるから楽しいのだけれど。
「Trick or treat」
夜の宴会も佳境に入ったころ、闇から浮かぶようにしっとりと黒い魔女が姿を現した。
「ああ、ロビンちゃん!これまたなんて魅惑的な登場の仕方ーっ」
昼間も確かに魔女の仮装をしていたけれど、月影さやかな夜空をバックに漆黒のドレスを身に纏ったロビンの姿は
まるで幻影のようだ。
「裾野に広がるきらめきが星みたいだよ、まさに夜の女王〜」
「ふふ、ありがとう」
くるりと背を向ければ、腰骨まで覗きそうなくらい大きく背中の開いたバックスタイルで、サンジは本日二度目の
鼻血を吹いた。
「・・・ロビンひゃん・・・い、悪戯されたい・・・」
「残念ね、私はお菓子が欲しいわv」
震える手で差し出したお菓子を軽く摘み上げて、ロビンは蟲惑的な微笑を残し闇に消えた。
「ああ〜つれない貴女も好きだ〜」
貧血のせいで常より更に白く冷たい指先で、サンジはゴシゴシと鼻を拭くと、ふらつく足取りでラウンジに入った。
さすがに今日は疲れた。
凄く凄く楽しかったけどな。
ナミとロビンの姿を頭の中で反芻しながら、ニヤニヤと一人で一服する。
宴会の喧騒は止んだようだ。
そろそろみんな、明日に備えて眠りに就く頃だろう。
「後片付けは明日にしようっと」
独り言を呟いたら、本日最後のモンスターが登場した。
「Trick or treat」
「・・・似合わねえ」
ぶっと噴き出すサンジにあからさまにむっとした顔をして、黒いマントを羽織ったゾロがのしのしと歩いてくる。
「なにそれ、お前のって吸血鬼?」
明らかに作り物の巨大な犬歯をそのままに、ゾロは勝手に酒を取り出すと封を開けた。
「大体吸血鬼ってのは、もっとスマートでダンディっつうか、紳士的っつうか・・・なあ?」
ちょっぴり酔っ払ったサンジのツボに入ったのか、一人ケラケラと頬杖をついて笑っている。
その向かいに腰掛けて、ゾロは首に巻いていたマントを脱いだ。
「実は別仕様でな、吸血鬼がお気に召さなきゃこっちはどうだ」
いきなり犬の耳をつけて立ち上がった。
いつものジジシャツ腹巻で、後ろに茶色の尻尾がついている。
「へ?なに?」
ナミで散々尻尾萌えしたくせに、ゾロの尻尾はピンと来ない。
「耳と尾っぽ、それに牙だ」
「あ〜狼男?」
うひゃひゃ〜と更にツボにはいって、サンジは笑い転げた。
「何それ、狼男って!月に向かって吼えてみろコラ。赤頭巾ちゃん気をつけて〜」
「気をつけんのはてめえだろ」
しょうがねえ酔っ払いだとばかりに、ゾロは傾いたサンジの身体を横抱きに抱えた。
「Trick or treat?」
いきなり耳元に低音で囁かれた。
笑いの形そのままに唇を止めて、サンジはたらりと冷や汗を流す。
―――お菓子をやらなきゃ、悪戯されちまう
勿論、ゾロの分のお菓子も用意してある。
がしかし、このまま渡すのは惜しいっつか・・・
惜しいってなんだよ!
一人突っ込みをしながらしばし固まっていたら、トテトテと可愛い足音が近付いてきた。
「Trick or treat―!」
現れたのは、コウモリの羽をつけたチョッパーだ。
寸でのところで、二人はバッと離れた。
「お菓子をくれなきゃ悪戯しちゃうぞ、ガオー」
「おいおい」
サンジは思わず苦笑を漏らす。
「なに言ってんだチョッパー、もう二巡する気かよ。朝いちでやっただろうが」
チョッパーは目をぱちくりとして首を傾げた。
「何言ってんだサンジ、俺がおねだりするのは今が初めてだぞ。だって、サンジにおやすみなさいを言うために
一番最後まで我慢してたんだから」
「―――へ?」
サンジとチョッパー、その間にゾロが入って三人はしばし沈黙した。
「Trick or treat?」
もう一度チョッパーが言う。
サンジはかくかくとした動きで、ゾロのために用意してあった菓子を取り出した。
「はい、どうぞ」
「ありがとう、んじゃ二人ともおやすみ!」
元気よく挨拶して飛び出していく、コウモリだかトナカイだかたぬきだかわからない後ろ姿を見送って、サンジは
ぎこちない動きでゾロを振り返った。
「・・・今ので、お菓子終了・・・」
ゾロは片眉を上げてから、口端もにやりと引き上げた。
「んじゃ、悪戯決定な」
「―――◇☆■#@□」
嬉し恥ずかしちょっと怖い
―――今夜はHalloween night
END