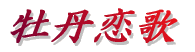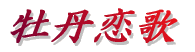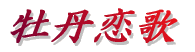表通りにできた小間物屋の隣に水茶店も開いて、毎日若い女衆で繁盛していると
使用人から聞かされて、ゾロは今度おたしと一緒に足を運んでみるかと思い立った。
おたしはゾロの許嫁で、この秋には祝言を挙げることになっている。
女は等しく甘いものが好きだろうし、ゾロ自身嫌いではない。
鍛錬した後の甘みは格別で、とろりとした黒蜜をかけたくずきりくらいなら丼一杯食べてもいいほどだ。
「評判ってえ、そこは美味いか?」
「ええ、味もよけりゃ職人の腕も見目もいいって話でさあ。なんでも若い男が
仕切っているらしいですが、娘っこには優しい上に実にマメで町民ながらなかなかの人気、付け文が
飛び代わってるってえ噂ですぜ」
ゾロは眉間に皴を寄せて、苦い顔になった。
それなら、おたしを連れていくのは止めとするか。
ともかく、どんな店かと友人エースを連れ立ってぶらぶらと大通りを冷やかしに歩いた。
一応武士の見栄として女子の溢れる店に足を踏み入れるのはやや気後れするが、同じ武家の出ながら
すでに身をもち崩した放蕩息子として持て余されているエースと一緒なら心強い。
「おたしちゃんのために下見に来る何座、ゾロも顔に似合わずマメだねえ」
「愚弄する気か?」
「からかってるんだよ」
裃姿に脇差を差しきちっと髷を結い上げたゾロと、派手な女物の着物を洒落に着こなしざんばら髪で歩く
エースとの二人連れは、街中でも大いに目立つ。
ゾロの両親はエースと付き合うことに表立って反対はしないが、苦々しく思っていることだろう。
しかしエースが嫡男であるポートガス家の主とゾロの父親は同期だったため、二人は幼い頃から自然と親しくなった。
親の教えを守り、幼少時より剣の道を極め勉学に励み真っ直ぐに成人したゾロと違い、エースは生まれ付いての
奔放な性格ゆえか、たいした傾奇者になっていた。
仕官の道は弟に譲り、早々に隠居してそのうち諸国を回る旅に出るのだという。
「先日も、お父上が我が父と語らい、嘆いておられたぞ。この親不幸者め」
「嘆いてくれる親がいるってえのはありがたいよ。けど俺の心は誰にも縛ることなどできないさね」
「・・・戯けものが」
いきついた先は、間口の狭い小さな水茶店だ。
隣の小間物屋も最近できてなかなかの品揃えで繁盛していると聞いていたが、その客がそのまま流れて
来るのだろう。
こちらも表の床几に零れんばかりの多くの人が腰を掛けている。
きゃいきゃいと娘たちの声がかまびすしい。
「ごめんよー。団子ふたつー」
エースが暖簾を掻き上げて、中に声を掛ける。
「あいよー」
威勢のよい返事が届いた。
若い男の声だ。
「男が一人で、切り盛りしてるのか?」
「ああ、こしらえるのも茶を淹れるのも運ぶのも全部一人でやってるらしい。けど不思議とこれが手早いってんで、
それもまた評判でさ。あんまり客を待たせちゃ、どんなに味が良くても足は遠退くからな」
「ふむ」
ゾロは空いた緋毛氈の上に腰を下ろして、手持ち無沙汰に隣の小間物屋に目をやった。
「あの店と関係があるのか」
「茶店の主人は元は小間物屋の主人だったらしいが、店が早々に軌道に乗ったもんで、手代に任せて自分は趣味で
ここを始めたらしい。ところがそっちがまた評判になって、結局二つの店が共にてんてこ舞いってことになったんだな」
「ほお」
なかなかのやり手と言うべきか、考えなしの一発屋とも言うべきか。
懐に手を入れて要らぬ世話を考えていると、店から前掛けをした男が出てきた。
「お待たせしました」
手には朱塗り盆。
たっぷりと大きな湯飲みに波々と注がれた茶が湯気を立てている。
素焼きの皿の上には、艶良く垂れがかかった団子が三串。
盆を持つ手の色の白さに目を奪われた。
盆が床几の上に置かれるのを目で追ってから、ゾロは顔を上げた。
男はもう一つの盆をエースの隣に置いている。
少し俯いた横顔は、長く伸びた前髪で表情が見えない。
ひょろりと背が高く、痩せた身体に紺地の着物がよく似合っている。
ぼうと見ている横でエースが代金を払うと、男は片手で受け取ってどうもと頭を下げた。
顔を上げた刹那、視線がかち合う。
手と同様に白い面。
片方だけ隠れた目元から覗く黒曜石のような瞳の奥底に、青白い炎が浮かんだ気がした。
寸の間、時が止まったように見詰め合い、男の方がふわりと笑みを浮かべる。
まるで花がほころぶような、柔らかで温かい、懐かしい笑顔。
ただ声もなくゾロはその顔を凝視して、再び頭を下げて店の奥へと引っ込む男の後ろ姿を阿呆のように見つめていた。
「どうしたんだ一体。おい、ゾロ?」
隣でエースが二人の成り行きを見守っていて、戸惑いながらも興味津々と言った風に話しかけてくる。
「ありゃ、ゾロの知り合いか?」
「いや、初めてだ」
「それにしちゃあ、なんだ今の意味深な微笑みは。明らかにゾロを見て笑ってたぞあの子」
「ああ・・・」
「女の客以外には、えれえつれねえってのも評判なんだぜ。男にゃつっけんどんで愛想もクソもねえってな。
それがまたどうしたこった」
エースは面白がってあれこれと話しかけてくるが、ゾロは何も答えられずただ眉間に皺を寄せて黙り込んで
しまった。
なんとも答えようがない。
あの男の顔を見た途端、なんとも言えぬ懐かしさと愛しさがこみ上げて来ただなんて。
愛しさ、だと?
わからぬ。
だが今己の心の中を満たす、この暖かいような悲しいような遣り切れぬ思いは、他になんと呼べばいいか
ゾロにはまったくわからない。
「まあまあ、そう考え込まずに。茶が冷めるぜ」
エースに促され、ゾロは上の空で団子を一串摘まんだ。
程よく焼けて香ばしく、柔らかな団子と甘辛い垂れの絡み具合が絶妙だ。
なるほどこれなら評判にもなろうと合点がいくが、ゾロの胸を満たしたのはそれ以上のことだった。
俺は、この味を知っている。
この団子を、食ったことがある。
いつだったか遠い昔―――
この団子もあの男も、俺は知っている・・・
不意に湧き上がった感情は、次第に確信へと変わっていった。
以来、ゾロはその茶屋に足繁く通うようになった。
いつも人で溢れているため、ゾロの定位置は表の床几の端だ。
しばらく通う内に、店に声を掛けずとも勝手に茶菓子が出てくるようになった。
ゾロは何でも好きだと知っているのか、その日によって品は変わるがどれも口に合い美味かった。
店の男は挨拶と礼だけを述べて、茶菓子を出すだけでさっさと店の奥に帰ってしまう。
それでも、ふと交わす目線とゾロにだけ向けられる微笑に歓迎されているのだと知れた。
「いらっしゃい、ああ今日はお連れさんと一緒で?」
顔を出した男は、ゾロの隣に若い娘を認めると慌てて奥に引っ込んだ。
程なく盆を持って出て来る。
「いらっしゃいませ、お嬢さんは初めて来てくだすったね」
「はい、とても美味しい甘味屋さんだとお聞きして、連れきていただいたんです」
おたしは器量よしで利発な娘だ。
ゾロと同じく武家の出で、年も二つしか違わない。
それ故に早く祝言を、と隣家からは急かされている。
「綺麗な娘さんだね、お武家さんのお嫁さん?」
町人らしい軽口だが男の目の色に不安が見て取れて、ゾロはなぜだか心苦しくなった。
隣でおたしは恥ずかしげに頷く。
「はい、この秋にそうなます」
「そう、おめでとうございます」
笑みを湛えたまま両手を揃えてきちんと頭を下げる男の、白い手元が震えていることをゾロは
見逃さなかった。
夜半過ぎ、ゾロは再び表通りまで来ていた。
普段は、日が暮れてからの他出などめったにせぬゾロだが、どうしても訪ねずにはいられなかった。
「邪魔するよ」
とうに暖簾の下げられた水茶店の引き戸に手をかける。
戸締りはきちっとされており、引き戸はがたつきはするが開かなかった。
声を掛けても返事はなく、裏口を求めて店を回るがそれらしき木戸はない。
小間物屋もしっかりと雨戸がを閉められ、叩いても応えはなかった。
―――ここに住んではいないのか?
しかし小間物屋と茶店を合わせてみると、なかなかの店構えだ。
奥に使用人くらい寝泊りしているだろう。
そう考えて勝手口を探そうと踵を返すと、俄かにゾロの足元が照らされた。
どこから灯りが漏れるのか、まるで誘うようにゾロの足先三寸ほどが明るく光る。
狐火か?
提灯もないのに自在に光るのは、それ以外考えられまい。
元々細かいことに頓着しないゾロは、これは便利だと導かれるままに歩いた。
いつしか大通りを抜けて、橋を渡り、稲荷神社の敷地にまで来ていた。
はてと首を傾げ辺りを見渡すと、いつの間にか狐火は消えてしんと静まり返っている。
月明かりが境内をほのかに照らし、闇を恐れることはない。
砂利を踏む音が聞こえて、ゾロは振り返った。
茶店の主人がいつの間に近付いたのか、すぐ傍に立っている。
「お前に、会いたいと思った」
ゾロは何の前置きもなくそう切り出した。
「毎日会ってるがな、客としてじゃなく話をしてえと・・・そうしたら灯りが点いたんでここまで来ちまった」
恐れもせず、訝りもせずにゾロはそう言い、照れた仕草で頭を掻く。
「てめえがここまで呼んでくれたと、そう思っていいんだろう?」
男は困ったように笑みを浮かべ、懐の中で腕を組み替える。
「何を仰いますやら。お武家さんがこんな夜中に町歩き・・・いや、神社詣でとは何事かなと、思って出てきた
だけですよ。狐にでも化かされなすったか?」
「そうか」
ゾロは当てが外れたと思ったか、露骨にがっかりした顔をする。
「まあいい、てめえに話があるっつったのは、これだ」
ゾロは袂から小さなものを取り出し、男へと差し出した。
その手の中のものを凝視し、男は信じられないといった風に目を見開く。
それは瑪瑙細工の根付だった。
色鮮やかな紅の牡丹が掘り込まれている。
「女物でもないのに牡丹でな、エースにでもやろうかと思ったがどうもしっくり来ねえ。それで、てめえを見たときから
なんとなく似合うんじゃねえかと思ったんだ。洒落物として持ってんのもいいだろ」
突き出された手のひらをじっと見据えたまま、男は石のように固まっている。
月の光の下で見るせいか、その顔は強張って青白い。
「気に入らんねえか?」
「・・・どうして・・・」
拒んでいる風には見えないが、ともかく驚いているようだ。
ろくに親しくない男から物を貰うなど、警戒されても仕方のないことか。
「あ、これは俺の剣の師匠の形見分けでもらったんだがな。どうも俺には似合わねえし、かと言ってこれが似合う
ような知り合いも俺にはいねえ。息子ができたらとでも思っていたが、てめえの顔を見たとき、ああこいつが
いいんじゃねえかと、そう思っただけだ」
他意はない。
本当に、一目見たとき似合いそうだと思っただけなのだ。
白く透き通る肌、輝く金の髪に青い瞳を持つこの男は、その身の内に紅蓮の炎のような激情を秘めている。
一輪の紅の牡丹はその冷たい容貌と対照的で、よく映えるに違いないと。
そこまで考えて、ゾロははっと気が付いた。
今、俺は何を思った?
この男が金色の髪だと、青い瞳だと?
そんなはずはない。
目の前にいるのは、色こそ白いものの黒髪に黒い瞳の優男だ。
一体俺は、誰のことを思い浮べたと言うのだろうか―――
一人でうろたえたゾロの前で、男は大切そうに両の手を差し出し、根付を受け取った。
胸に当て、愛しげに目を伏せる。
「覚えて、いてくれたのか?」
震える声に、ゾロは惑ったままその顔を見返した。
なぜだ、俺はこの男を知っている。
知っている、とその男が目で訴えてきている。
知っているはずだ、何度も何度も夜を共にし、生きて、死んだ
誰よりも愛しい―――
「あ・・・」
ゾロは声を上げ、それからやにわに手を伸ばして男の身体を抱き締めた。
同じくらいの上背だが、痩せた躯はすっぽりと腕の中に収まる。
「あ、サンジ」
「ゾロ会いたかった・・・」
まるで波が一気に押し寄せるかのように、色んな記憶がゾロの脳裏を駆け巡った。
初めて出会った平安の都
牡丹の咲き乱れる中庭で、ゾロは初めてこの世ならざらぬモノと出会った。
金色の髪、青い瞳、透き通るような雪の肌。
美しい、狐の妖―――
「お前は、俺が人でないと知った上で、娶ってくれた」
「お前は化けるのが上手かったからな、誰もお前を怪しむものはいなかった。中睦まじい夫婦として暮らすことが
できた」
「たったの五年だったけれど・・・」
人間の命は儚い。
ゾロは流行り病で若くしてこの世を去った。
また再び逢おうと、サンジに言い残して―――
「それから俺は人の世に留まり、ずっと待った。お前が再び生まれ変わるのを、ずっと待った」
そうしてそれから二百年後、サンジは再びゾロと出会った。
牡丹の刺青を入れたゾロは、この身体ごとてめえにやるとそう言って、サンジを抱いた。
身分も格式もない二人は野で暮らし、愛を育んだ。
なのに――――
合戦に巻き込まれてゾロは死んでしまった。
二人で暮らした年月は、僅か二年だった。
また何百年も月日が流れ、牡丹の振袖が縁で巡り逢った時、ゾロは呉服屋の番頭だった。
やはり一目見てお互いがわかり、サンジは娘に化けて所帯を持った。
早々に暖簾分けされて、仲睦まじく呉服屋を営んでいたのも束の間、大火に見舞われゾロは
店と共に焼けてしまった。
人の区別もつかぬほど焼け爛れた遺体を寺に運んだのはサンジだ。
物言わぬ真っ黒な炭の塊を前にして、サンジは涙が枯れるまで泣いた。
泣いても泣いても、悲しみは止まらなかった。
人の命はあまりに儚い。
いつも取り残されるのは自分ひとり。
次はいつかと、また逢えるのかと思い焦がれる心はいつでも張り裂けそうで、せっかく手に入れた
幸せは指の間から零れ落ちる砂のようにあっという間に流れて消えてしまう。
なんて、せんのない恋をしているのだろう。
再び三度巡り逢えても、また失う悲しみを知るなら、もう逢わぬ方がよいのに。
人の世から姿を消して、己の領地で悠久の時を安穏と生きればいいことなのに、サンジはどうしても
人の身のままで待ち続けてしまう。
そしてとうとう、百年前に、サンジは人違いをした。
ゾロだと思って恋い慕い、所帯を持つ寸前までいった男は、実はゾロを殺した悪党だった。
ゾロは、自分と出会う前に短い命を散らしていたのだ。
もう止めようと、本気で思った。
また生まれて巡り逢えたとしても、ゾロは必ず先に逝く。
ならばもう、逢わなくていい。
今まで共に暮らしたゾロとの想い出を胸に、これからは妖として身を隠し、穏やかな日々を送るのだ。
人も妖も、星の数ほどこの世にいる。
恋をしたければ、新しい相手を探せばいいだけのこと。
故郷に戻らず人の世に住み続けるサンジを慕い、数千年もの間ずっと傍にいてくれる妖もいる。
いい加減、ゾロのことを諦めて妖としての安穏な暮らしをすればいいものを、いつまでもうろうろと
迷い続け探し続ける自分を、傍らからそっと見守ってくれている妖がいるのにも気付いている。
けれど、サンジはゾロを探すことを止める事ができなかった。
きっとまた逢える。
そしてまた別れが来る。
それでも
それでも―――
自らに言い聞かせ思い悩みながらも、サンジは結局里で暮らした。
人通りの多い町中に店を設け、名前を変え店を代え、転々と居場所を移し暮らし続けた。
いつゾロがこの世に生を受け生れ落ちても、また巡り逢えるように。
いつしか戦に明け暮れた世は遠退き、平穏な人々の営みが続くようになった。
サンジは西国の地に落ち着いて、小間物屋を開いた。
程なく店は軌道に乗り、ほんの手遊びに隣に店を広げ茶店を開けば、そちらの方も繁盛する。
すでに三千年を生きるサンジは大妖となり、付き従う眷属も多く、手助けには事欠かなかった。
そうして幾つもの眠れぬ夜を数え、果てなく続く悶々とした日々を過ごしながら、また再び
二人は逢えたのだ。
「ゾロ・・・」
喜びに胸を震わせながらその名を口にしたサンジは、けれど抱き締めるゾロの背中にその腕を
回そうとはしなかった。
胸元に両手を添え、そっと押しやる。
「サンジ?」
うつむいたサンジの表情は、長い前髪が隠してしまって何も窺えない。
今は漆黒に光る髪は、月の灯りを照り返して銀髪のようだ。
「サンジ、どうした?」
懐かしい名を呼ぶ声に、サンジはたまらず口元を覆った。
ともすれば、嗚咽が漏れそうになってしまう。
せっかく逢えたのに
ようやっと、巡り逢えたのに・・・
「サンジ、なぜ泣く。俺だ、ゾロだ。覚えているぞ、またこうして巡り逢えた。」
抱き締めようとする手を振りほどいて、サンジは後退りした。
白い頬に、涙の筋が光って残る。
「だめだゾロ、やっと逢えたのに・・・」
「駄目?何がだ」
「てめえがだ。てめえには、おたしちゃんがいるじゃないか!」
はっとして、ゾロは目を見開いた。
今ここでサンジと巡り逢えたと気付いた刹那、大量に流れ込んだ記憶で随分と混乱したが、
今は武士の身の上で、しかも許嫁がいるのだ。
「サンジ・・・」
「しかも、お武家さんだよな。小間物屋を営んでる俺とは身分も違わあ・・・。お互い、自由に
生きていた頃の二人じゃねえ」
そう言って、サンジはまた一歩下がった。
「こうしてまた逢えただけで、俺は満足だ。てめえが元気そうで、立派な屋敷で育ったことは
見届けた。幸せに暮らせよ」
「てめえ、このっ・・・」
いきなり身を翻し逃げようとするサンジを、ゾロは咄嗟に追いかけ力強く腕を掴んだ。
そのまま引き倒す勢いで、身体に抱きとめる。
「勝手なことばかりほざきやがって、せっかく逢えたのに、んじゃさいならって、それで終わる気かよ!」
ゾロに掴まれて、サンジは顔を背けて手足をばたつかせた。
ガツンと脛を蹴られたが、ゾロには痛みより怒りの方が勝る。
「てめえコラ、こっち向きやがれ。何一人で結論付けてやがんだ。俺を、俺を見ろ!」
背けられた顎を掴み、無理やり仰向かせる。
月の光に照らされた双眸には、うっすらと涙が浮かんでいる。
「てめえ、俺と別れたくねえだろう?」
ゾロはぎりぎりと歯軋りをしながら、唸った。
「俺は、おめえと離れたくねえ。また逢えたんだ。こうして逢えた。逢えたからには、もう離れねえ。
てめえが妙な遠慮しようが気を回そうが、んなもんクソくらえだ。家がなんだ、おたしが何だ。
俺はすべてを捨ててでも、てめえと添い遂げる」
「・・・また、すぐにいなくなるくせに!」
いきなり口を開き、サンジが叫んだ。
「そうしててめえと暮らしても、すぐにてめえはいなくなるんだ。いつだって、そうだ。残されるのは
俺一人・・・てめえと暮らした家で、てめえの想い出だけを抱いて、ずっとずっと俺は一人取り残される」
「サンジ・・・」
ずるずるとその場にへたり込み、サンジは砂利の上に手を付いた。
「もう、止めにしようって何度も思った。もうこれきり、てめえのことは忘れて妖として生きようって。
なにもかも、いい想い出として心に残して、てめえのことは、もうこれきりに―――」
細い肩が、小刻みに震えている。
「なのに、どこにいて誰といても、てめえの面影を探しちまう。今もどこかでてめえが生まれてや
しねえか、死んでやしねえかと、そう思えば胸がはち切れそうになる。俺の知らないお前、俺が
知らぬ間に生まれ生きて、死ぬお前。俺は何度、お前を失くせば気が済むんだろう。何度取り残される
悲しみに暮れれば、てめえのことを忘れられるんだろう。俺には・・・」
地べたに這い蹲り、拳を打ちつけ慟哭する。
「俺には、てめえと出会う以外の救いは、ねえのかよっ」
細くたなびくような嗚咽が漏れた。
地面に突っ伏して泣くサンジの背中を、ゾロは立ち尽くしたまま見守っている。
長く長く、永遠に続くかもしれない出会いと別れ。
幾度も死に変わり巡り逢い、出会いの喜びよりも別れの悲しみばかりが募る、残酷な邂逅。
ゾロは瞑目し静かに息を吐くと、ゆっくりと瞳を開いた。
月の光の下、震えて嘆く背中が見える。
何かに縋るように伸ばされた白い手は砂利に爪を立て、苦悶の筋を浮かび上がらせている。
こんなにも嘆き悲しむ恋人は、けれど確かに、今目の前にいるのだ。
「サンジ」
ゾロはしゃがみ、サンジを優しく抱き起こした
いつまでも顔を上げない痩せた肩を、何度も何度も繰り返し撫で擦る。
「サンジ、それでも俺はてめえに逢えた」
こうして逢えた、それだけで・・・
「お前が愛しい。一目見て、すぐに思い出した。理屈ではない、てめえの姿を見たその時から、もう
俺の生は決まったんだ。今の家も両親もおたしも、もう俺にはなんの意味も持たない」
「ゾロっ」
サンジの声には叱咤が含まれている。
けれどゾロは耳を貸さない。
「俺は、俺はてめえに出会うために生まれて来た。言えるのはそれだけだ。だから、これからの
俺はてめえのもんだ」
「・・・ゾロ」
「俺は、お前のために生きる。お前と共に生きて暮らし、その胸で死なせてくれ」
「・・・ゾロっ」
ようやく顔を上げたサンジは、零れんほどに目を見開き、はらはらと涙を流し続けている。
濡れて開いた唇に己が口をそっと近付け、ゾロは万感の思いを込めて口付けした。
「ゾロ・・・」
柔らかい草の上にサンジを押し倒し、ゾロは首元に顔を埋めてその匂いを存分に嗅いだ。
焦がれて求めて愛しくて止まぬ相手が、今、自分の腕の中にいる。
どうしてこの男のことを忘れて、今まで安穏と暮らしていたのか。
そんな自分が今では信じられない。
こんなにも愛しい存在はなかったのに。
「サンジ」
何度も口付け、深く吸った。
着物の合わせ目から手を差し込み、柔らかな肌のぬくもりを求める。
サンジはかすかに背を撓らせて、ゾロの愛撫に身を捩る。
月の光の下で、徐々にサンジの姿が変化していく。
漆黒の髪は透けて輝き、金色の光を弾いた。
固く瞑られた瞳がゾロの口付けに誘われるように開かれ、月の光を青く照らし返す。
「ああ―――」
ゾロはサンジの上に馬乗りになって、感嘆の声を上げた。
これこそサンジだ。
何百年何千年と、何度も巡り逢い愛し合った、美しき妖―――
数千年の時を経た大妖は、夜露に濡れた花びらのようにしどけなく横たわり、震えている。
この肌を、身体を、何度愛しても満たされることはない。
ゾロもまた、永遠の渇きの中でサンジの面影を求め続ける。
襟元を肌蹴け、すでに色づき硬くなった乳首に舌を這わせる。
わき腹を撫で腰紐を解き、もじもじと擦り合わせる膝を割って、太腿を撫でた。
「ゾロ・・・」
サンジの口から、切なげな吐息が漏れる。
「もう止めようなどと、言ってくれるな」
囁きながら、ゾロは何度も唇を合わせた。
「生まれ出でてもお前がおらねば俺は狂う。狂うて見失って、死ぬことも忘れるやも知れぬ」
指の腹で乳首を捏ねられ下腹を擦られながら、サンジは乾いた笑い声を立てた。
「狂うなら、俺のがとうに狂っているよ。寝ても覚めてもお前のことばかり・・・死ぬことすら、叶わぬ」
笑い続けるサンジを組み敷いて、ゾロは喉笛に歯を立てた。
「今度身罷る時は、いっそこの手で連れて行こうぞ。お前が俺を忘れて他の者と共になるなど、
到底許せぬ」
サンジの喉を震わせる含み笑いが止んだ。
「今度こそお前を連れて逝く。俺はお前だけのものだ。何度も生まれ変わり死に変わり、永遠に求め続け、
結ばれても一つにはなれぬ」
「ゾロ―――」
サンジの足を肩に担ぎ上げ、掌に唾を吐いてゾロは乱暴に擦り付けた。
「俺を忘れることなど、許さぬぞ。この身は果てても幽鬼となりて、お前の傍にいよう。なれるものなら
狐火でいい。その髪の一筋を濡らす朝露でもいい。お前の傍にいられるならば、未来永劫―――」
「あ、あああっ、ゾロ」
強引な繋がりを、サンジは悦びをもって迎えた。
今この場にゾロが生きて、此処に在る。
それだけがすべてで、もう構わない。
「ゾロっ・・・好きだ。忘れるなんて、できない!」
「俺もだ、サンジ・・・このまま共にっ・・・」
どうしてこんなに惹かれ合うのか、どうしてこんなにも求め続けるのか。
答えなど見つからぬまま、二人はお互いを貪り続ける。
これを恋と呼ぶのなら、それはあまりにも惨くいたわしい。
東の空が白々と開け始め、朝露に濡れた木々を風が優しく揺らしている。
明け方まで睦み合った二人は、稲荷神社の境内で寄り添って、互いの熱を冷ましていた。
「ゾロ、もう夜が明ける」
「ああ」
サンジを抱く手に力をこめて、ゾロはまっすぐ前だけ向いて言葉を綴った。
「俺は、家を出る。」
「けれど・・・」
「もはや俺には、家も親も大切なものではない。お前と共にのみ生きていく」
サンジはゾロの胸に顔を凭れさせてまま、ゆるく首を振った。
「だめだ、許婚のおたしちゃんが・・・」
おたしは気位の高い女だ。
許婚に出奔されたら、自害しかねないだろう。
だが・・・
「かまわぬ。俺にはもはや、お前しかおらぬ」
言い出したら聞かないところは、何度死んでも直らない。
サンジは困った顔つきのまま、それでもゾロに小さく頷いて見せた。
その日、小間物屋は突然店を畳み行方知れずとなった。
時を同じくして、ロロノア家の嫡男ゾロが行方知れずとなる。
悪友のエースに誑かされてでもしたかと、家を上げての大騒ぎとなったが、結局行方は
ようとして知れなかった。
一人残されたおたしは潔く大橋から身を投げようとしたところを、通りすがりの武士に
助けられ、後にその男と夫婦となる。
事がうまく運んだ背景には、西国に残ったサンジの眷族の計らいがあった。
そして大江戸――――
どこから上京したのか、一組の若夫婦が「長崎屋」という回船問屋を開いた。
小さいながらも商売は繁盛し、あれよあれよという間に店を広げ、いつしか町の大店として
名が通るようになる。
若夫婦は仲睦まじく実直に働いたが、添って五年後に一人娘に恵まれた。
妊娠したと知った時の女将の驚きようは尋常でなく、隣近所からの祝いの言葉にも目を
白黒させていたほどだ。
長い人生、たまには信じられない奇跡もあるというもの。
おたえと名づけられたその娘は、やがて江戸一番の弁天様と呼ばれるほど美しく成長し、
年頃になり婿を取った。
これで長崎屋も安泰かと思われたが、若夫婦にはなかなか子宝に恵まれなかった。
ようやく授かった一人息子は三日と生きずに亡くなり、一家は悲嘆に暮れ、ついでに娘婿の
隠し子騒動で揺れた後、更なる悲劇が長崎屋を襲った。
大女将としてすべてを取り仕切っていた「おさん」が、突然この世を去ったのだ。
年齢を感じさせない若さと気風のよさ、そして美しさで長崎屋を切り盛りしていた大女将の死は、
店や家族に大打撃を与えた。
火の消えたような寂しい雰囲気の中にあって、長崎屋の主人ゾロだけはいつも矍鑠として、
妻の死を悼む素振りも見せず飄々と暮らしている。
そしてようやく長崎屋に訪れた春―――
おたえが玉のような男の子を出産した。
紅の夕暮れが、障子に長い影を落としている。
庭からは、楽しげに笑う孫の声。
身体の弱い子だが、しっかりとした兄やたちに見守られ、優しく育っている。
これでもう思い残すことはないなと、ゾロは床に横たわったまま、静かに目を閉じた。
「お父上、おやすみですか?」
おたえの声が耳に心地よい。
薄く目を開けると、おさんによく面差しの、愛しい娘が穏やかに微笑んでいる。
「うむ、温めの白湯を持ってきてくれるか」
「かしこまりました」
しとやかに頭を下げ、音を立てずに部屋を出て行く。
その後ろ姿を見送って、ゾロはまた目を閉じた。
枕元に、愛しい者の気配を感じる。
「そこまで老いぼれたてめえを見るのは初めてだな」
声が中空から浮いて聞こえた。
「俺も、ここまで生きたのは初めてだったな」
目を閉じたまま笑いを漏らし、ゾロは深く息をついた。
「だがもうそろそろだ。思えば良い人生だった」
「ゾロ」
目を開き、唇に笑みを湛える。
初めて出会った時と同じ、愛しい金色の妖が傍らに座っている。
「荼吉尼天様は、よくしてくださるか」
「ああ、良い方にお仕えできた。一太郎も授かったし、人の世で暮らすより俺には性が合っている」
「おたえは・・・」
「藤兵衛がついているから安心だろう。ちょっとばかし考えの足らない大馬鹿者だが、
おたえを思う気持ちは本物だ」
「一太郎は」
「あればかりはどうにも危なっかしいが、仁吉と佐助がついているから大丈夫だろうよ。
俺も時折様子を見に来る」
「そうか・・・」
もう何も遣り残したことはないのだ。
サンジと出会い、すべてを捨てて江戸まで出てきた。
店を構え、驚いたことに子まで授かり、跡取りもできた。
もはや、この生に何の未練もない。
「また、しばしの別れ・・・だな」
「ゾロ・・・」
サンジが、布団の中に手を差し入れ、枯れ枝のようなゾロの腕を掴んだ。
「荼吉尼天様が、庭番を探しておられる」
「・・・・・・」
「なにせ広いお庭でな、四季を問わず花が咲き乱れ、樹々が繁る美しい庭だ。だが、時折小鬼や
邪気どもが入り込んでは悪さをして、困っておられる」
ゾロは目を閉じたまま、耳を傾けている。
「それらを見つけては懲らしめ、追い出してくれぬか」
ゾロの口元が、ふっと笑いの形に歪んだ。
「小鬼と言っても六尺は背丈がある。邪気など気配だけで本体を持たぬ。なかなか手ごわいものどもよ」
「退治し甲斐があると、言うもの」
「ゾロ・・・」
「・・・うむ」
「失礼いたします」
跪き、両手で障子を静かに開けておたえが顔を覗かせる。
「お父上、白湯をお持ちしました」
応えはない。
ゾロは先ほどと同じ寝姿で、布団の中に横たわっている。
穏やかな表情で目を瞑る姿に、おたえは目を細めた。
「よく、お休みですか?」
布団からはみ出た指先に、そっと触れる。
おたえは後ろに控えていた女中を振り返った。
女中は顔色を変えてさっと立ち上がり、廊下を早足で走り去った。
「お医者様!源信様をっ」
俄かに慌しくなった長崎屋の屋敷の中で、おたえはゾロの枕元に正座し、開け放たれた障子の
向こうを静かに見やった。
おさんの血を引くおたえの目には、はっきりと映っている。
紅に染まる雲の向こう
若い姿のゾロとサンジが、共に手を携え――――
微笑みながら消えて逝った
おわり