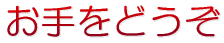「嘘だろ....」
ドアを開けたサンジは思わず声に出して言った。
「まさか....」
足元に視線を落とすと、どこから見ても女物の白いサンダルがあった。
ほんの30分ほど前、ロッカールームで。
コックコートのボタンを外そうとしても、うまく指が動かない。
それが動揺しているせいだと気付いたのは、それからしばらく経ってから。
落ち着け...。サンジはそう自分に言い聞かせる。
今日のゾロの行動や言動、態度....色々と考え合わせてみて、どんどん思考が悪い方へと流れていくのだ。
いや、考えすぎだろう...。
とにかく早く帰って、メシを作って待とう。
そして話は、さらに2時間ほど前に遡る。
サンジがシェフとして働くホストクラブでは、今日も大勢の客が来ていた。
ただ最近、常連の一人---サンジのホスト時代に一番よく来てくれていた客---ナミが姿を見せない。
ほんの30分ほど時間が空いたから、と言っては顔を出してくれていた。
そしてサンジが裏方へ回ってからも、変わる事なく通ってくれていたのを、当たり前の様に考えてきた。
週に一度は顔を見ていたのに、もうかれこれ3週間は会っていない。
「Aの2番、ご指名です」
A-2...一見様お断りのVIP席の一つ。一日に一人か二人、予約が入る。指名を告げに来たボーイが待機中の
ホストの一人へ視線をやった。
俺か?と少々面倒臭そうにホールへ出たのは、この店指名率NO.3のゾロ。サンジがホストを辞めてシェフに
なった後、チーフ兼スカウト担当のシャンクスが自らの手で発掘してきた逸材だ。
ゾロが向かった先には、足を組み直しながら、"遅いわねぇ"と言わんばかりの表情で待つ女、ナミがいた。
「よう」
「それだけ?」
「....本日もご来店ありがとうございます」
ったく....その棒読みはワザとでしょ?ナミはくすりと笑った。
「今日はね...分かってる?"ご指名"したのよ?」
「あァ....?」
やっぱり分かっていないようだ。ただ、今まで通り、席に呼ばれただけだと思っている。
「私ずっとフリーだったでしょ?でもね、たった今決めたのよ....」
本指名すれば、そのホストが辞めない限り、指名替えはできないルールになっている。いわゆる"永久指名制"だ。
そして指名されたホストは誠心誠意、接待に努めなければならないのは当然の事。
「決めたって、何を?」
「バカねっ....あんた此処に来て何ヶ月経ったと思ってるのよ!本当、サンジ君もちゃんと教えときなさいよね....」
「またサンジか....あぁ、いっぺん訊いとこうと思ってたんだが」
「何よ?」
「.....まだ、好きなんだろ?アイツの事」
「....なっ....何よっ....改めて言わなくてもいいじゃない。そりゃ、あんたから奪い返したいって思ってたけど.....」
「今はもういいのか?」
「....しょうがないじゃない。サンジ君、もう私の方なんか見てないんだし」
「.......」
「だいたいねっ....こうなったの、あんたのせいでしょっ?何をしれっとした顔で」
「俺のせいなのか?」
「本っ当、あんたって馬鹿で鈍感でデリカシーのない男ねっ!」
「うっ....」
馬鹿とか鈍感とか言われた事はあるが、三つ並べて言われたのは初めてだ。
「私はね、言っちゃ何だけど、ここの常連で太客なのよ?どれだけ店に貢献してると思ってんの?その客をもっと
大事にしようとは思わないの?」
「......お前がアイツの話をするからだろ」
「....話を大きくしたのは、あんたじゃない?」
「......忘れたいのか?」
「え?」
「アイツを忘れたいってんなら.....協力する」
「.......協力って.....」
ナミの方に視線を移したゾロ。いつもナミの席に居る時は、どちらかというとヤル気のなさそうな目をしているが、
今は別人のようだ。
ナミはサンジを忘れたいなどと思った事はない。
(一体何を勘違いしてんだか....)
そもそもサンジが奥へ引っ込んでからも、こうして足繁く通っているのは何の為なのか。新入りのゾロに、他の
ホストには無い何かを感じて近付いたのはいいが、全くなびいてこようとしない。
ナミは決して自信過剰と言う訳ではなかったが、彼女の誘いに反応を示さない男はゾロが初めてだった。
そしてそのゾロに大切な人を奪われてしまった。いや、本人には奪ったという自覚は全くないのだが。
「ゾロ....?」
ゾロの手がナミの方へ伸びた。手の甲をすっと撫でると、細い手首を軽く握った。
「ん?」
手首ごと、身体を引き込まれた。ゾロの胸の中に納まる格好で、ナミがもたれかかる。
顔のすぐ横には、ゾロの唇が迫っていた。
「ちょっ....離して...」
「行くぞ」
「行くって...」
「とにかくここを出る」
「!」
まだ店に来て30分と経っていない。
「ねぇ?大丈夫なの?」
「あァ?何が」
「お店....まだ上がれる時間じゃないでしょ?」
「いいんだ」
「それに....」
ナミが見ている方にゾロが目を向けると、ワゴンを押して歩いているサンジの姿があった。ちょうど、指名された
席へ向かっているところだった。
いつものナミなら、店に来れば真っ先に、キッチンにいるサンジの顔を見に行く筈だった。たまたま調理の
真っ最中だったから、遠慮したのだった。
「気になるのか?」
「ううん....」
「じゃ、出るぞ」
ちょうどグラスや氷などを運んできたウェイターを捕まえ、ゾロは一言二言耳打ちすると、ナミの腕を掴んで店を出た。
「5分だけ待ってろ」
「ええ....」
ナミを待たせたまま店に戻った。早足で歩くゾロの慌しさに、不思議そうな顔でサンジが見ていた。
「....ゾロ?」
「.....」
「早ぇな....こんな時間からアフター?」
「まぁな」
「ほどほどにな」
「あぁ....じゃ、な」
「メシは....」
帰ってから食うのか?と訊こうとしたが、ゾロはそそくさと出て行ってしまった。
「....とりあえず作っといてやるか」
サンジはワゴンを押して歩き始めた。と、その瞬間。
「この、香り....」
ナミがいつも付けているトワレ。ずっと前になるが、二人で一緒に選んだ香りだ。それ以来ずっと使っているの
だから間違う筈も無い。
まさかな、とサンジは呟きながらキッチンへと戻った。そしてそこに丁度来ていたウェイターに訊いてみる。
「今日、ナミさん来てたか?」
「え?あ、来てましたよ」
「誰が行ったの?」
「ゾロさんご指名でしたよ」
「指名?本指名?」
「そうみたいです」
「.......」
「どうかしましたか?」
「いや...何でもねぇ」
「サンジさん、顔色が...」
「大丈夫だ、悪かったな...そこ置いといてくれ」
ウェイターが引き上げたグラス類を受け取ると、カウンターに置いた。
ゾロが通用口から出ると、出口近くでナミが待っていた。立ち止まる事もなく、ゾロはそのまま歩き出した。
ナミも付いていく。
「.....ねぇ?」
「ん?」
「.....大丈夫?」
「何が」
「絶対、サンジくん気付いてると思うけど」
「かもな」
「....って、それ、かなりマズイんじゃないのぉ?」
「別に」
「....おかしいじゃない!ね?何があったの?喧嘩してるの?」
「うっせぇな...」
「何?もしかして当てつけでこんな事してんの?」
「あー!違ぇよっ....そんなんじゃねぇ」
「....今まで私が飲みに誘っても、来なかったじゃないの」
「あー、あれは気が向かなかっただけだ」
「だから、私は客だって!それを断るってどういう神経?」
「.....お前、いつもそんな調子なのか?」
「え?」
「いつも....そんな風にウルサイのかって」
「何よ....あんたがさっきからオカシな事ばっかり....」
ナミがふと気づいたように言う。
「ゾロ?まさかとは思うけど.....」
ナミが何度か歩いた事のある道順。最後に来たのはいつだっただろうか。
(サンジくん....あの先にある信号の所で、よく煙草吸ってたわね...)
蘇ってくるのは、そんな日常よくある風景ばかり。サンジと過ごした楽しかった日々。しかし、ナミはすぐに
現実に引き戻され、そしてゾロに詰め寄る。
「協力してくれるんじゃなかったの?」
「ん?」
サンジの事を忘れるどころか、余計色々と思い出してしまってるというのに。
「一体どうしたら、そんなに鈍くいられるわけ?」
「あァ?何だ」
「こんなの....忘れろって言う方が無理よ!本っ当、あんたって馬鹿ね!」
「うるせぇな」
一瞬だが眉間にキュッと皺を寄せたゾロ。ナミの腕を取り肩を引き寄せると、ギリギリまで顔を接近させ、口角だけで話す。
「どんな場所だろうと関係ねぇ。俺が」
「....?」
「忘れさせてやる」
「.....馬鹿よね、あんたは」
挑むような眼差しをゾロに向けると、ナミはゾロの唇にキスをした。何の感情もこもらない、乾いた行為。
「本っ当、気が強ぇよな....」
この勝気で、いつも自分を馬鹿呼ばわりする女を、黙らせる方法はないものか。少し離れかけた唇に、もう一度近付いた。
ナミがその大きな目で、ゾロの行動をじっと見ている。
---さぁ、次はどうしたいのよ?
そう言ってるかのような、強い表情で。何だか勢いをくじかれたゾロは、それ以上近付くのをやめた。
ふぅ、と溜息を小さくつきながらゾロは足を止めた。目の前には見慣れた高層の建物。エントランスホールへとそのまま向かう。
ナミの腰に手を回すと、さっさとゾロはパスナンバーを押してロック解除し、エレベーターへと進んだ。足音がコツコツと
反響している。
「もう、離して」
ナミは腰に添えられたゾロの手を引き剥がした。
「別に逃げたりなんかしないわよ」
逃げる?何でそんな言葉が自分の口から出たのだろう?ナミは動揺する。
エレベーターに乗り込むと、ゾロが階数のボタンを押した。この光景も何度も見た。階数も部屋の番号も覚えている。
「悪ぃけど....」
「え?」
「俺、あんまり巧くないからな」
「なっ...何がよっ」
「こんな事なら、もうちっと教わっときゃ良かったぜ」
「だから...っ」
そう言いながら、ナミはまた少し動揺している自分に気付く。
エレベーターを降りると、端まで歩く。またナミの頭の中に浮かんでくる過去の光景---サンジはゆっくり歩いて
ナミをエスコートしてくれた。でも、目の前のこの男は一人で歩いているつもりなのか、物凄い速度で進んでいく。
(こんな男があの店でNO.3だなんて、信じられないわ)
それでも、何となくここまで付いてきてしまった。
ゾロが鍵を開け、部屋のドアを引く。
「入れ」
「....」
ナミの背後でドアが閉まる。カチャン、とロックがかかる音。
「ま、適当に座っててくれ」
「.....」
ナミは部屋を見渡した。以前と変わらない壁の色。男の二人暮らしとは思えないほど、綺麗に片付いていて、
家具の配置もほぼ変わらず。変わったところと言えば、ソファに置かれたクッションが増えている事くらいだろうか。
また当時の光景が浮かぶ。そう、部屋に入るとすぐサンジはキッチンへ向かった。そしていつもコーヒーを淹れてくれた。
合間合間に何度もナミの方を気遣い、決して一人にはしなかった。
「これくらいだったかな....」
ゾロが何やらブツブツ言っている。キッチンの中でコーヒー豆の入った袋を片手に、少し困ったような顔をしている。
「ゾロ?」
「お前、分かるか?」
「え?まぁ、そのスプーンで2杯もあれば充分だと思うけど....」
ゾロが何だか頼りなげに見えて、ナミは助けに入った。自分がした方が早そうだった。
「私がするわ」
「あ、あぁ....頼む」
いつもコーヒーを淹れるのは、サンジの役割だったから、あまり要領が分からなかったのだ。
それにひきかえナミは、いつもサンジがするのをよく見ていたから、今回初めてした気がしなかった。
ミルで挽き終えた豆をドリッパに入れると、コーヒー液が落ちてくるまでしばらく待つ。
ナミは、その数分間の待っている時間が好きだった。あの時は....。
「......」
「.....」
「そんな悲しそうな顔するな」
「....そんな....」
(優しい声で言わないでよ....)
ナミは涙が出てきそうな気がして、思わず目頭を指先で確認した。
「何よ、ゾロのくせにっ.....」
「あーそうかよ....悪かったな」
そう言ったゾロの表情は、柔かかった。静かにナミに近付いてくる。
逞しい腕がナミの身体を包んだ。
コーヒーの香りが漂ってくる。またあの時の光景が浮かんでくる。
「ねぇ....もう少し、こうしててくれない?」
「あぁ」
「でも変なコトしないでよ?」
「ンな事言うんだったら、離れろ」
「いやよ」
「....お前な、そんなに身体押し付けといて、何もするなっつう方がオカシイだろ!」
「したいの?」
「.....別に」
「何?私じゃそんな気起こらないって訳?」
「ったく、うるせぇ女だな」
今度はゾロからキスをする。少し長めで、でも少し軽めで。
「....ゾロのくせに...」
「あァ?」
「見かけによらず、巧いじゃない」
もっと無骨で、荒々しいのかと思っていたら。
ナミは不覚にも、その優しさに鼻の奥が痛くなってきた。
背中に回された腕の心地よさに、思わずゾロの胸板に頭を預けた。好きとかいう感情は一度として抱いた事が無いのに、
胸が熱くなる気がした。
「あ、コーヒー出来上がったな」
「.....そうね」
リビングでくつろぎながら、ナミは時計を見て言う。
「そろそろサンジくん、帰ってくるんじゃない?」
「あぁ」
「私、居てもいいのかしら?」
「いいんじゃねぇの」
「ゾロ....」
「ん?」
「やっぱり諦めるの、やめる」
「....?」
「サンジくんは返してもらうわ!」
「ただい....ま」
「おう」
「サンジくん....」
玄関のドアが開いたのにも気付かなかった。
かなりの至近距離で会話していたゾロとナミ。
何の先入観も持たずにその光景を見たら、普通に仲の良い恋人同士のようだった。
「あ、な、なんだ....ウチ来てたんだ」
「....」
「それだったら言ってくれたらいいのに....ゾロ?」
ナミがソファから立ち上がった。
「私...そろそろお暇するわ」
「ナミさん...ゆっくりしていくといいよ。別にそんなに慌てて帰らなくても」
「また...いつか改めてお邪魔するわ」
「そ、そう?せっかく来てくれたのに....」
「じゃ、またね....サンジくん」
「あ、そこまで...」
「ゾロ!送ってくれる?」
「....あぁ」
何で俺?みたいな顔をしながら、ゾロは立ち上がった。サンジの視線を感じる。
「ちょっと行ってくる....ナミをタクシーに乗せたらすぐ戻る」
「俺、邪魔だったか?」
「つまんねぇ事言ってねぇで、メシ作って待ってろ」
「おい、何だその言い草はっ....」
ゾロが部屋から出て行くと、しんと静まり返った。
「一体どうなってるんだ....」
「もしかして、部屋に戻ったら喧嘩になっちゃうのかしら?」
「いや、大丈夫だ」
「きっと疑心暗鬼になってるわよ?」
「面倒臭ぇな....」
「ちゃんと説明してあげなさいよ?」
「何でそこまでするんだよ」
「きっとサンジくんの事だから、悪い方へ考えるような気がするのよね」
「別に知らねぇ女連れ込んだ訳でもねぇのにか?客を連れて帰るのって、珍しくも何ともねぇだろ」
「....馬鹿ね」
「お前なっ...何回馬鹿っつったら気が済むんだっ」
「だって馬鹿だもん」
ゾロが呼んだタクシーが来たらしい。
「一度別のお店でゆっくり飲みたいわ」
「あぁ、考えとく」
「じゃ、おやすみなさい。コーヒーご馳走様」
「気をつけてな」
乗り込む直前、ナミがゾロの頭を引き寄せた。唇をギリギリまで寄せて言う。
「実は、此処、部屋からよく見えるのよ」
「お前、そんなに俺たちを喧嘩させてぇのか?」
意味ありげにこちらを見ながら、ナミは去っていった。
部屋に戻ると美味しそうな匂いが漂っていた。サンジはゾロの方を見る事もなく、いそいそと働いている。
「お、何か急に腹減ってきたな....」
「何にも腹に入れてねぇのか?」
「コーヒー飲んだだけだ」
「お前が淹れたのか?」
「あ、あぁ...そうしようとは思ってたんだがよ....」
「ん?」
「ナミがやってくれた。助かった」
「そうか...."見るに見かねて"ってところだろ?」
「まぁな....意外と手際が良くってな....勝手知ったる何とやらってやつか」
「もう昔の話だ」
「俺の知らない....お前を知ってるって訳か」
「何だ?今さらそんな事」
「さっき...」
テーブルを拭き、カウンターに並んだ料理を運びながら、ゾロは続けた。
「やっぱり...お前のこと、"返してもらう"....ってハッキリ言ってたな」
「.....」
「聞いただろ?」
「....うん」
「俺たちが一緒に居る限り....」
「じゃ、どうするんだ?」
「どうにもできねぇけど....何かアイツ見てて痛々しいって言うか」
「馬鹿だな」
「なっ....お前までそんな事言うのかっ」
「何?ナミさんにも言われてんのか?ははっ....」
「くっ....」
「ナミさんは、そんな弱い女の子じゃねぇよ」
「でも.....」
ついさっきの、腕の中に居たナミは、本当に儚げで小さくて弱々しかった気がしたが。
「お前、試されたんだよ」
「は?」
「どれくらい、俺の事、好きかってな」
「....どういう意味だ?」
「ンなの、てめェで考えろ」
---説明なんて、そんな野暮な事させんじゃねぇよ。
(ったく鈍感でデリカシーのねぇ男だぜ)
「なぁ?ところでさ」
ベッドの中、隣に居るゾロに向け、サンジが話し始めた。
「何で、二人でウチに来る事になったんだ?」
もうその事には触れないのだろうと、勝手に思っていたゾロは一瞬言葉に詰まった。
「いや....何でだろうな....よく覚えてねぇ」
「嘘つけ、ちゃんと覚えてんだろ?お前が酔っ払う訳ねぇし、ナミさんはお前より酒は強いんだからな」
サンジは、天井を見つめるゾロの頭に手を伸ばし、自分の方へ向かせた。
「.....ナミはきっとお前の事、忘れたがってんだと思ってな」
「ん?」
「もう、お前からは相手にされてないって....言ってた」
「.....」
「じゃ、俺が.....忘れさせてやろうと思って」
「.....で、強引にお持ち帰りか?」
「強引って.....ほどでもねぇけど.....」
サンジの手がゾロの柔かい髪を撫でた。
「そういうの、お節介って言うんだよ」
「別に俺は....」
「最後まで責任取れねぇんだから、あんまり世話焼かねぇ方がいいぜ」
「じゃ、どうしてやればいいんだ」
「だから、何もしなくていいんだって....時々話し相手になってやってくれ」
「.......心配じゃねぇのか?」
「心配したってしょうがねぇだろ?」
少し前までは、不安で動揺していた事は内緒だ。
「でもナミさんは...."ゾロならいいかも"って思ってるだろうな」
「はァ?」
「嫌だったらウチまでついて来ねぇだろ?」
「.....」
「でも、多分そんな事にはならねぇだろうな」
「何でだ?」
「....彼女は、本当に惚れてる相手にしか許さねぇからだ」
「言ってくれるじゃねぇか」
「あのナミさんが、お前に本気で惚れる訳ねぇだろ?」
「.....ほざけ」
「ん?それとも何か....あったのか?」
不敵な笑みを浮かべたゾロを見て、サンジは内心少しだけ心配になってきた。
ゾロにしても、今回に限り、ナミの事を一瞬でも可愛いと感じてしまった事は内緒だ。
「いや....大した事はねぇ」
「何だよ....気になる言い方しやがって」
「ふん、やっぱり心配なんじゃねぇか」
「ちげぇよ....ただ」
サンジはゾロの方へとにじり寄っていく。
「やっぱり女の方がいいや...とか...お前が言い出すんじゃねぇかと思って」
「馬鹿か、てめェ」
(お前の方こそ....)
サンジの方こそ、いつだってナミとヨリを戻せそうな状態にある。
普段はお互いそんな事は考えないようにしているが、時折ふと不安になるのだ。
「俺がそんないい加減な気持ちで、お前と居るとでも思ってんのかよ」
「それを言うんなら.....俺だって」
サンジが目線をゾロに向けようとした瞬間、唇が塞がれた。と同時にゾロの腕が背中に回されてきた。
「こっちはとっくに覚悟決めてんだからよ....もう後戻りできねぇ、ってな」
「ゾロ.....」
「お前も...そんくらいは覚悟しとけ」
「そんなの....最初からしてるさ」
「.....」
「お前に初めて会った時からな」
ゾロの腕の中のサンジは、その広い胸に頭を押し付けた。何か今日は色々あって混乱したが、もうそんな事の全てが
どうでも良くなった。しなやかな金色の髪が、ぱらりとゾロの上腕に流れ落ちる。
ゾロの厚く大きな手が、サンジの頭に載せられた。髪を指で梳きながら、薄い色をした睫毛の生え際から瞼にかけて、
唇を這わせた。サンジはゾロの後頭部に手をやり、顔を上げると、喉元から顎にかけて何度も口付けた。
「んっ」
「どうした?ゾロ」
「くすぐってぇ」
「そっちだって...」
互いに焦れったくなったのだろう、顔の位置を少しずつずらしながら唇を近づけ合った。触れ合った瞬間、
何度も吸い付く音がして、次に舌を絡めあうとさらに隠微な音が続いた。
「んっ...はぁ」
息苦しさ、せり上がる熱、早まる鼓動....
白い胸を上下させながら、呼吸を整えるサンジ。
「おい、まだ何もしてねぇぞ」
「何だよ、お前は平気そうな顔して」
「今からこんな調子だと、この先どうなるんだろうな?」
「...今日は激しいのはナシな」
「俺はいつも優しくしてやってるだろ」
「....."いつも"じゃねぇけどな」
サンジの記憶にある限り、ゾロに酷くされた事は皆無だった。それどころか、物足りない時だってあった。
(どっちかっつーと、激しいのは俺の方だな....)
そんな事をとりとめもなく考えていると、ゾロの声がすぐ耳の傍で聞こえた。
「何、考えてる....」
「ん?何って....お前の事に決まってんだろ」
「で、どうする?」
「どうって?」
「...俺がしていいのか?」
「......」
即答すれば、"待ってました"みたいな感じがして、ちょっと癪に障る。答えを無闇に渋れば、"何を勿体ぶってんだ"とか
言われるかも知れない。
(何を、迷ってんだ...俺は?)
「疲れてんなら....止めとくか?」
「べっ...別に疲れてなんか...」
言葉とは裏腹に、ゾロの手はサンジの身体を撫で下ろしている。サンジの背中からぞくりとした感触が、身体の中心部へと
集まってくる。無意識の期待感で、腰が浮き上がってしまう。
「....なんてな。止める訳ねぇだろ」
ゾロの乾いた唇が重なってきた。反射的にサンジが差し出した舌先が、ゾロの口内にそろそろと入っていく。入った途端、
あっけなく捕まった。
「んん...」
強く吸われ甘噛みされ、なかなか離してもらえそうになかった。と、同時にゾロの右手はサンジの浮いた腰の下に入り、
左手は下腹部をさらに滑り下りる。
「んんっっ...」
口を塞がれているので、思うように声が出せない。腕を掴まれて少し痛かったが、ゾロは構わず手を動かし続けた。
手の中のサンジ自身は硬く勃ち上がり、下着から先端を覗かせていた。その柔かい部分だけを、親指の腹でゆっくりと撫でる。
「はっ...んっ....ゾロ...」
やっと唇を解放され、目を潤ませるサンジ。こんな中途半端な愛撫にいつまでも焦らされるのは正直辛い。
「手抜きすんなよ....」
辛うじて強気な言葉で牽制する。腰を少し浮かせてみると、ゾロが"分かってる"といった表情で、ニヤリと笑いながらサンジの下着を膝下までずらせた。
「もうこんなに硬い....」
手の平全体で握りこみ、ゆっくりと上下に動かすと、それにつられるようにサンジの腰が揺れる。半開きの唇から少し
掠れた甘い声が漏れた。
「んあっ.....ぁっ.....」
その声に、ゾロ自身も反応する。思わず小さく溜息をついた。手の動きを徐々に速めてサンジの反応を窺う。
「ゾ...ロ....」
「ん?」
「.....観察してん、じゃ...ねぇ....」
「お前が感じてるの、見てるだけだろ」
「何で...自分だけ見てんだ」
「んあっ...」
サンジも手を伸ばしてゾロの下腹部へ滑り込んだ。堂々と反り返っているゾロ自身がひっかかって、片手だけでは下着を
脱がせるのに一苦労だった。
「何で.....こういうところまで偉そうなんだ」
「知らねぇよ...んっ」
「ゾロ....ちょっとおめぇの手、休めとけ」
「あァ?何で?」
「このままだったら....俺先にイキそう....だしよ」
「イったらいいじゃねぇかよ」
「ンなの....」
確かに、もうかなりヤバイところまでキている。今、思いっきりゾロにシてもらったら.....どれほど気持ちいいだろう。
(でも....)
「おし、分かった....じゃ、しばらく手ぇ止めとく」
ゾロは手の動きだけは止め、サンジ自身をじっと握ったままにした。
「ほら、もっと俺の触れ」
「なっ....もうちょっと言い方ねぇのかよ....」
「他にどう言うんだ?」
「何か....違ぇような....」
不満を口にしつつも、サンジはゾロを愛撫し始めた。ゾロの体は、さっきからのサンジの声と表情に煽られていたせいで、
感度が上がっていたためか、少し触っただけでも息が上がってきている。
(何だよ...おめぇも同じか....)
すぐにサンジの手が濡れてきた。手を動かしていくにつれ、さらに濡れてくる。
「んっ...ぁ...」
「ゾロ....」
今度はサンジの方が、煽られる。正面からゾロの感じてる顔を見るのは、かなり久しぶりだった。
(コイツ...こういう時はホント、別人なんだよな...)
ゾロの手の中で、ドクンと脈打つ。全く手は動いていないのに、触られているのかと錯覚する。サンジは焦れったくなり、
腰を動かしてみた。途端、快感が勢い良く湧き上がってくる。
「あっ...ヤバイ....ゾロ、俺っ...」
「俺....も....んっ....」
「あああぁ....っ」
「んっ...んぁ....」
互いの腹を、白濁の体液が濡らした。
「.......はぁ....」
「....はっ.....はっ.....」
(今の何だよ....)
信じられないくらい気持ちよかった。ゾロも....同じみたいだった。そして先に回復したらしいゾロが、飛び散ったモノを
拭き取りながら、真面目な顔つきで言った。
「これで終わりじゃねぇぞ」
ゾロに両膝を割られ、正面からじっと見られている。サンジは思わず膝を閉じようとする。
「なっ....」
「隠すな」
「何か、おめぇ、エロいって!」
「手もどけろ」
放出した直後だから、力を失っていたサンジの分身も、こうして見られているうちに、起き上がってきてしまった。
ゾロは薄っすらと笑い、舐めるような視線を向けただけで、何もせずサンジの股間のさらなる奥地へと顔を埋めた。
「んんっ....」
「どうした?」
「ひっ....そこで喋んなよっ」
「え?何だってー?」
「...てめっ....わざとやってる...だろ」
ゾロの舌がサンジの奥の窄まりに触れる度、腰が引けるような、何とも言えない感触が走る。その舌のざらつきと
ぬめり具合にだんだんと慣れ、心地よくなってきたその時。
「うぉっ?!」
「ひぁっ!」
な....何だよ?驚かすんじゃねぇ!そう言おうと思ったが、声が裏返りそうだったので、言葉を呑み込んだ。
「おい.....サンジ」
「んぁ?」
快感のせいで、何となく艶かしい声音で応える。
「今日...何曜日だ?」
「.....へっ?」
「土曜日....だっけか?」
「う....ん。土曜日だ。今は土曜日の早朝」
「....てことは、これから寝て起きたらまた仕事だよな?」
「おう」
「.....一日間違えた」
「.....ん?」
「今日は....ヤル日じゃねぇだろうが」
「はっ....今頃そんな事」
二人の間には、いつの間にかそんなルールができていた。時間を気にせず思いっきり楽しみたいから、抱き合うのは
土曜か日曜の深夜から明け方。とは言え、まだヤリたい盛りの男二人。それ以外の日でも、どちらかが誘えば自然に
始まってしまう。
「しょうがねぇな...ここまでだ」
「おいっ....こんな中途半端なトコで止めんなよ」
「俺は寝ないと駄目なんだ...知ってっだろ」
「俺は余計眠れねぇよ」
「.....おめぇも....一日間違えてたのか?」
「あ....いや、俺はちゃんと分かってた」
「気付いてたんだったら、何で言わねぇんだよ?」
「お前が....曜日間違えてるなんて思わなかったからさ」
あぁ、ヤリたいんだな、と単純に思っただけだった。そしてサンジにも特に断る理由もなかったから。
「ふぁ....寝ようと思った途端、本当に眠くなってきやがった」
「おいっ....マジもう寝ちまうのかよ」
「結構遅いぜ....いつもの時間に起きれなくなるだろ」
「.....はぁ...完全に睡眠モードだな」
「....明日...な」
「ん?」
「......明日、今日の分も入れて、いっぱいシテやる」
「.....っ、いや別に今日の分はリセットしとくから、いいよ....。さ、もう寝ろ」
「おう、そうか....じゃ...寝る......」
「.....ゾロ?」
「................」
「.....もう寝た?いくら何でも.....早....」
「ぐがー......」
ゾロが目覚めると、ほぼ例外なくサンジが先に起きている。朝食をいつも作ってくれている。そして今日も、
気持ちよく起きたものの、何やら違和感に気付く。
「ん???」
右の手の平がベタベタする。ところどころはパリパリした感じで、よく見ると指の間にはティッシュペーパーの
千切れたようなものがくっついていた。
「.....」
右手は使った覚えはない。
「....あっ....」
そっと匂いを嗅いでみると、それは覚えのあるものだった。愛おしさすら感じる。
「ん?俺、寝惚けてたのか?」
寝惚けたら右手を使うのか?サンジが傍に居たら、そう言われるに違いない。
いくら考えても分からないゾロ。とりあえずベッドから下りる。
「おい、メシ冷めるぞー」
サンジが呼んでいる。
「手もシッカリ洗えよー」
意味ありげに言ったつもりだったが、ゾロは気にも留めていなかった。
あれこれ深く考えない。それがゾロの良い所なんだろう。
「だったら....」
---だったら、またこれからも使わせてもらうかな。本当、気持ちイイんだよな...ゾロの手って。
そんなことを考えながら、淹れたてのコーヒーをテーブルに並べているサンジ。これを飲めば、少しはゾロの頭も
すっきりするだろう。
どうぞ素敵な週末を。
fin.
おしゃれでで小粋なゾロサンをありがとうございます。!
[1]タイミングが悪い[2]段取りが悪い、要領が悪い[3]飲み込みが悪い...等など思いつく限りの悪いモノ尽くしのゾロを書いてくださったとのこと(笑)
ゾロってほんとに、どんな職種についてもマイペースで、なおかつサンジに甘やかされてるんだろうなあ。
ドキドキ音世界を垣間見せていただいたようですっかりときめいてしまいました。。
こちらの作品は、ホストクラブが舞台の「青い薔薇」シリーズとして、本編があるようですので、ぜひそちらもお楽しみくださいv